
みおりんさんに聞く
著書や、ユーチューブチャンネル「みおりんカフェ」などでノート術を発信している東京大学卒の勉強法デザイナー・みおりんさん。1年にわたる自宅での浪人生活を経て、東大合格をつかんだ一つのかぎが、ノートを活用した勉強でした。その基本やポイントを聞きました。
家と学校の4種類を活用、強い味方に
Q(質問) ノートをどのように活用していましたか?
A(みおりんさんの答え) 勉強に使うノートといっても、さまざまな種類があります。中学生の頃、私は次のように四つに分けていました。
学校で作るノート
❶授業ノート 学んだ内容をわかりやすく整理する
おうちで作るノート
❷演習ノート 実際に問題を解いてみたり、スペルを書いてみたりと力試しをする
❸間違い直しノート テストや問題集などで間違えた問題だけをまとめる
❹まとめノート 苦手な部分だけをまとめる
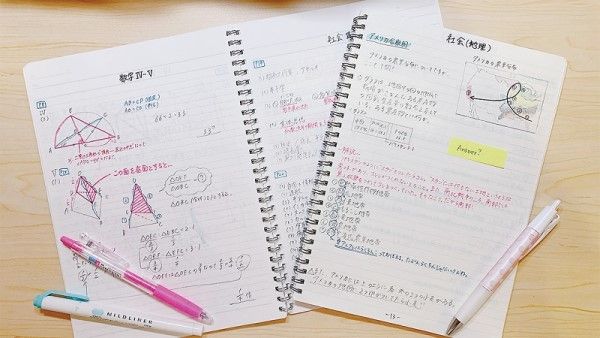
❸❹は、効率的に自分の苦手な部分を見直すことができます。高校生になると、この二つを1冊にまとめた暗記ノートという形にするなど、アップデートしていきました。
Q おうちで作るノートは教科別に分けるのですか?
A 全ての教科を1冊にまとめるのがおすすめです。1冊にまとめることで情報を一元化でき、苦手な部分を見直しやすくなるほか、持ち運びもしやすいと思います。
読み返すことを意識

Q ノートをとるポイントは?
A だらだらと文章を書くのではなく、「見出し+箇条書き」で書くのが基本です。
演習ノートは書いて終わりで大丈夫ですが、授業ノートや間違い直し、まとめノートは読み返すことが前提です。読み返すことを考えて見やすく書くようにしましょう。
Q ペンの色はどのように分けるとよいですか?
A 私は、授業で初めて知ったことは赤、すでに知っていたことは緑、単語や用語の意味は水色、和訳や現代語訳、その他のポイントなどは青のペンとしていました。自分の中で色の意味を決めておくと、使う色も絞られてきます。
時間がないときは、赤ペンで書かれたところを中心に見直すなど、文字の色を見るだけで情報の種類や重要度を認識できます。
Q 他に心がけたいことは?
A 授業ノートなら、先生の豆知識や雑談、自分が感じたことのメモを書くのもおすすめです。授業の光景が思い出しやすくなると、授業の内容も思い出せるからです。
文字だけではわかりづらいものもあるので、イラストを描いたり、描けないものは教科書や資料集などからコピーしてノートに貼ったりしましょう。
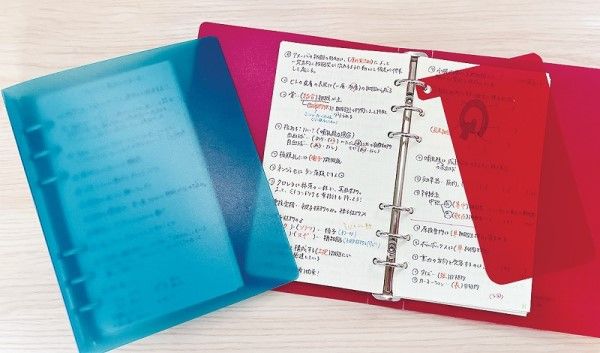
「勉強の冷凍保存」しておく
Q そもそも、なぜノートをとるのでしょうか?
A 授業を受けただけでは、全てを覚えたり理解したりすることはできません。ノートに書くことで、後からおさらいできる良さがあります。私は「勉強の冷凍保存」と呼んでいます。
複雑な内容や図にしないとわかりづらいようなものも、ノートにわかりやすく「見える化」することで、自分の頭の中の整理にもつながると思います。
Q 中高生へメッセージを。
A あくまでノートをとることは手段。書いて満足するなどノートを作ることが目的になってはいけません。
ノートを活用した勉強は、書くのは3割、読み返したり解き直したりするのが7割程度だと意識しましょう。ノートを自分の味方にしていってください!
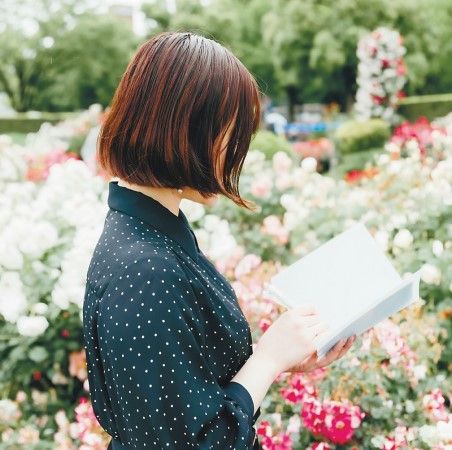
みおりん
1994年生まれ。著書に『モチベも点数もめきめきアップ! 中学生のおうちノート術』(実務教育出版)、『東大女子のノート術 成績がみるみる上がる教科別勉強法』(エクシア出版)など。
(朝日中高生新聞2025年3月30日号)
朝日中高生新聞は週1回おうちに届きます!
デジタル版は初回申し込み1か月無料!今すぐ読めます!
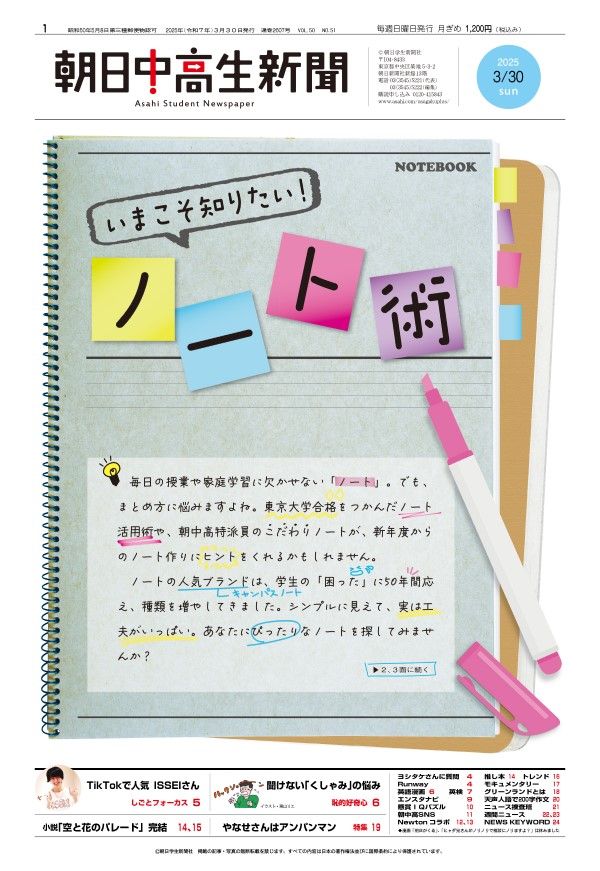
朝日中高生新聞は、忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回お届け。定期テストや調べ学習にも最適です。進路などお悩み相談やここでしか読めない漫画も。学校や塾では学べない知識が身につきます。
紙面版「朝日中高生新聞」は、日曜日発行/20~24ページのボリュームでご自宅にお届けします。デジタル版「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版で、週1回配信。デジタル版はバックナンバーも読めます!

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。




