
同性婚を考える G7で唯一、法的保障ない日本
日本はなぜダメ?
同性カップルを家族と認める法的な決まりがないのは、主要7カ国(G7)のうち日本だけ。 「結婚したい」と思ったすべての人が、性別を問わず婚姻関係を結ぶことができる「婚姻の平等」の実現を望む人がたくさんいます。 当事者の思いや日本の制度の課題などについて取材しました。
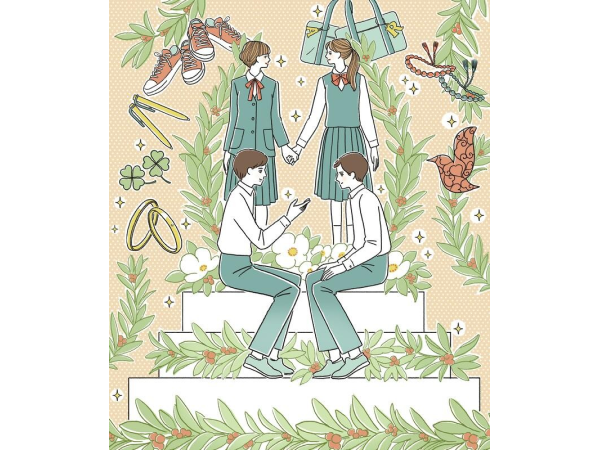
婚姻の平等を求めて
日本の同性婚をめぐる課題は、今年2月の元首相秘書官による差別的な発言をきっかけに注目度が高まりました。まずはニュースを振り返り、日本の今の状況を伝えます。
首相側近による差別発言に批判
同性同士での結婚は、2001年に初めてオランダで法制化されました。裁判の判決で事実上認められたところも含めると、30以上の国や地域に広がっています。19年には、アジアで初めて台湾が同性同士の結婚を認めました。

日本は性的少数者のLGBTQをめぐる対応が各国より遅れていると指摘されています。主要7カ国(G7)の中で同性カップルの法的な保障がないのは、日本だけです。
今年2月、岸田文雄首相は、同性婚を法律で認めることは「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だ」として、慎重な姿勢をみせました。
その後、首相の広報役などを担う荒井勝喜首相秘書官(当時)が、性的少数者や同性婚について、「隣に住んでいるのもちょっと嫌だ」などと差別発言をしました。
国の政策にも関わる人物からの差別発言に国内外から批判の声が相次ぎました。荒井氏は発言を撤回し、岸田首相は荒井氏の首相秘書官の役職を辞めさせました。
差別の禁止、権利を保護する法整備を
これを機に性的少数者への差別禁止や同性婚の法整備を求めるオンライン署名が始まり、当事者らは今月12日、約5万6千件をLGBTに関わる法案をまとめる議員連盟に提出しました。
5月に広島で開かれるG7首脳会議(サミット)で性的少数者の声を届けようと、日本の当事者3団体は先月、東京都内で国際会議「Pride7サミット」(P7サミット)を開催。性的少数者の権利を保護する法整備を求めるなどの方針を確認しました。
裁判所の判断割れる
同性同士の結婚をめぐっては、19年2月、同性カップルらが「結婚の自由をすべての人に」と、札幌、東京、大阪、名古屋の四つの地方裁判所で国を相手に裁判を起こしました。その後、福岡でも提訴され、これまで、札幌、大阪、東京の3地裁で判決が出ています。
国側は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて」とある憲法の文章について、「両性という言葉は男女を表していて同性婚を想定しておらず、異性の婚姻と同じように保障する必要はない」と主張しています。また、「伝統的に、婚姻は生殖と密接に結びついて理解されている」と解釈し、同性カップルには子どもが生まれないことも、主張の根拠にしています。
21年の札幌地裁の判決では、「法の下の平等」を定めた憲法に違反していると判断。22年の東京地裁判決でも、「違憲状態」にあると判断されました。一方、22年の大阪地裁判決は、憲法に違反しているとは認めませんでした。
今後、5月に名古屋、6月に福岡で判決が出されます。
同性婚
同性同士で法的に婚姻関係を結ぶこと。最近は、だれもが望んだ相手と結婚できるようにする「婚姻の平等」と言われることが増えています。
LGBTQ
女性が好きな女性「L(レズビアン)」、男性が好きな男性「G(ゲイ)」、両性を好きになる「B(バイセクシュアル)」、心と体の性別が違うことを表す「T(トランスジェンダー)」といった性的少数者の頭文字をとった略称です。「Q(クィアまたはクエスチョニング)」は、性的指向・性自認が定まらない人のことです。
(朝日中高生新聞2023年4月16日号)

「朝中高プラス」は朝日中高生新聞のデジタル版です。忙しい中学生、高校生のために主要なニュースを週1回配信。定期テストや調べ学習にも最適!学校や塾では学べない知識が身につきます。





