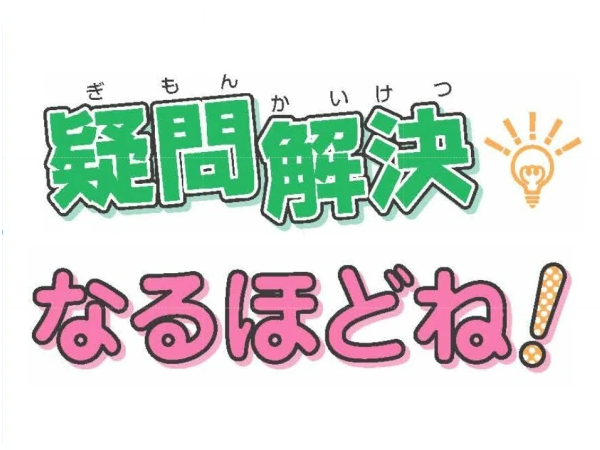
読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回はSさん(埼玉県・1年)から寄せられた「冷やすとなぜくさりにくくなるの?」という質問に答えます。
Sさん(埼玉県・1年)
夜ご飯が終わって、お母さんがカレーを冷蔵庫の中に入れていました。どうして食べ物を冷たいところに入れるとくさりにくいんですか?
NPO法人 カビ相談センター 久米田裕子さん
食べ物は微生物の活動によってくさります。10度以下に冷やすと、食べ物についた微生物は活動しづらくなるので、くさるスピードを遅らせることができます。20~40度くらいが微生物の好きな温度です。
10度以下は微生物が活動しづらい
室温は微生物増える
質問に答えてくれたのは、NPO法人カビ相談センターの久米田裕子さんです。「食べ物は微生物の働きによってくさりますが、10度以下に冷やすと微生物が活動しづらくなり、くさるのを遅らせることができます」と説明します。
くさらせる微生物は、私たちの生活環境に一緒に暮らしています。あたたかくて湿気のあるところが大好きで、えさとあたたかい温度、適度な水分があると、どんどん増えます。
増えた微生物は食品を食べて分解します。分解がすすむと嫌なにおいがしたり、変な色や味になったりします。これがくさった状態です。
微生物は20~40度くらいを好みます。今の時期、35度をこえる日もありますが「室温だとあっという間に増える」と久米田さん。食材や調理した食品はすぐ冷蔵庫に入れましょう。さらに冷凍してしまえば、微生物の活動は止まるそうです。
カレーを食べる時に気をつけたいのが、食中毒の原因になる微生物、ウェルシュ菌です。この菌は、環境により姿を変えるという特徴があります。土の中や動物の腸などにいる菌で、生きづらい環境になると「芽胞」という種のような姿に変わります。そして、生きやすい環境になるのを待ち、その時がくると発芽して増えるのだそうです。
2日目カレーはグツグツ再加熱
長持ちする保存食は
「カレーはタマネギやジャガイモなど土で育つ野菜や肉を入れるので、菌が入りやすいんです。芽胞は熱にとても強く、グツグツ煮こんでも死にません。機会をうかがう芽胞が発芽するのは、調理後のカレーが冷めて45度くらいになった時。目覚めて発芽し、どんどん増えます」
つまり、2日目のカレーには、発芽した芽胞が増やしたウェルシュ菌がたくさんいる可能性があります。食中毒対策として久米田さんがすすめるのは、カレーが指でさわれるくらいの温度になったら、すぐに冷蔵庫へ入れること。
さらに、「2日目に食べる前に、グツグツと再加熱してください」。そうすれば、増えたウェルシュ菌は死ぬので安心して食べられます。芽胞が残っていても、芽胞は種としてそのまま体から出るので、食べても被害はありません。
微生物の働きで食べ物がくさるのだとしたら、ヨーグルトや納豆などの発酵食品も、くさっていることになるのでしょうか。
久米田さんは「微生物が働いて変化する点はどちらも同じ」と言います。「ただ、それが人にとっていい変化か悪い変化か、で呼び名が変わります。発酵食品はいい変化です。微生物の働きで栄養が増えて、長持ちする保存食として、冷蔵庫ができるずっと前から活用されてきました。


他にも、食品をくさらせずに長持ちさせる例として、乾燥させたり、塩漬けや砂糖漬けにして水分を減らしたりするなどの工夫があります。みなさんも身の回りで、食品保存の知恵を探してみてください」(戸井田紗耶香)
(朝日小学生新聞2022年8月9日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。





