
読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回は小学生3年(大阪府)から寄せられた「車酔いをするのはなぜ?」という質問に答えます。
小学生3年(大阪府)の疑問
ようちえんのときは車酔いをしなかったのに、さい近よく車酔いをします。なぜ車酔いをするのか教えてください。
東京医科歯科大学教授 堤剛さん
脳は目から見える景色、耳で感じとる動きやかたむきなどの情報を合わせて体の動きや向きを理解しています。車などで動画を見ていたり、読書をしていたりすると目から入る情報と耳や体から入る情報にちがいが生まれ、乗り物酔いにつながります。
脳が受けとる情報のミスマッチで起こる
車内では動画を見ないで
車やバスに乗っているときめまいがしたり、気分が悪くなったりした経験がある人もいるでしょう。このような症状は乗り物酔いの可能性があります。
乗り物酔いのしくみにくわしい東京医科歯科大学教授で耳鼻科のお医者さんの堤剛さんは、脳が受けとる情報の「ミスマッチが原因」と説明します。一体どういうことでしょうか。
私たちの体がどっちを向いているか、どんな動きをしているかは脳が理解しています。目から見える景色、耳で感じとる体の動きやかたむきなどの情報を合わせて導き出しています。
Mさんは車の中で動画を見ているときに酔いを感じたそうです。堤さんは、動画が原因でミスマッチが起きたのではと考えます。
車に乗っていると体は車からゆれを受けます。脳は耳のおくにある耳石という部分のほか、筋肉や関節の動き、皮膚からそのゆれや動きを感じとっています。一方、動画を見ている目は、「自分の体は止まっている」とする情報を脳に送ります。
脳はそれらの情報を合わせて判断しますが、受けとった情報がちがう場合、自分の体の正確な動きや位置をとらえることが難しくなります。その結果めまいが起こり、気分が悪くなったと考えられるそうです。

車で酔わないための対策はあるのでしょうか。堤さんは車の中では動画を見たり、読書をしたりしないことだといいます。そしてこう付け加えます。
「窓の外を見るようにしてください。車の運転手はふつう酔うことはありません。常に外を見ているので、脳が動きを正確にとらえられるからです」

外を見ることは症状を和らげることにもつながります。適切に酔い止めの薬を飲むことも大切です。
乗り物酔いは子どもに多い
車の長い振動が胃や腸に伝わることで気分が悪くなる例もあります。もともと情報を処理するのが苦手な人や、ストレスを抱える人も同じような症状が出ることがあるそうです。
一度車の中で気分が悪くなると、同じ車に乗る度に症状をくり返すケースがあるといいます。そんなときは、「いつもとちがう状況をつくってみてください」と堤さん。窓を開けて風を入れかえたり、温度を変えてみたりするといいそうです。
乗り物酔いは子どもによく見られるといわれます。なぜでしょうか。堤さんは「子どもは動きを読みとる機能や情報を処理する力が未発達だからです」。中学生ごろになると生活でさまざまな動きも経験し、自然と落ち着いてくることが多いといいます。
夏休み中、いろいろな乗り物を利用する人もいるでしょう。目線を手元に集中しすぎないことが大切です。堤さんは「家族の人とよく相談して対策を考えてください」と話します。
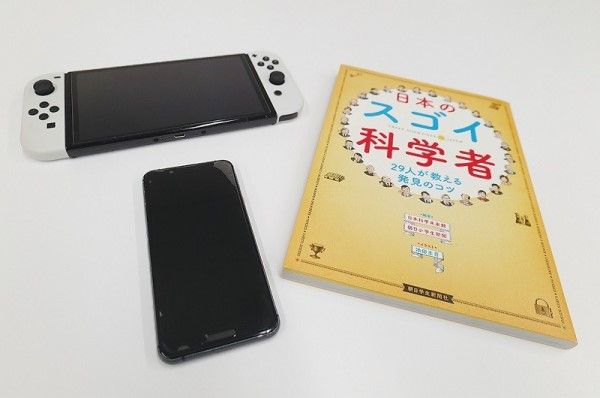

(正木皓二郎)
(朝日小学生新聞2023年8月1日付)




