
2024年度の中学入試について、国語の入試ではどのような文章(書籍)が出題されたのでしょうか。朝日学生新聞社編集部では各地の中学から問題を入手。出題が集中した作品のいくつかを紹介します。(山本朝子)
物語文 主人公の心の動きを読み取る
物語文は、いまの中学生の気持ちを現代の社会状況のなかでえがいた作品が多い印象。「ジェンダー(性別にかんする社会的な差)」や世間の「ふつう」からはみ出すことへの違和感などを取り上げた作品がその一例です。
◇
『成瀬は天下を取りにいく』(宮島未奈・著/新潮社)はコミカルな要素が盛り込まれた青春小説で、個性的な少女(成瀬あかり)の中学2年生から高校3年生までの日々がつづられています。おもな舞台は実在する進学校の滋賀県立膳所高校です。
栄東(埼玉)は成瀬たちが高1のときに足を運んだ東京大学のオープンキャンパスの場面を取り上げ、文脈に合う会話文や、ある場面で感じた気持ちの理由などを選択させました。豊島岡女子学園(東京)は高3の場面と、回想としてオープンキャンパスの場面を引用し、時期が異なる二つの文章から登場人物が何年生の何月の話かを読み取らせたり、共通する思いを選ばせたりしました。中央大学附属(東京)は中2の夏休み、閉店することが決まった百貨店に成瀬が通う場面からの出題。本文の内容を要約し、解釈を加えた文章の空欄を埋める形式の設問でした。
『成瀬は天下を取りにいく』
宮島未奈・著/新潮社

わが道をいく性格の女子生徒、成瀬あかり。地元の百貨店が1か月後に閉店することを知ると毎日通うなど、中学2年生から高校3年生までの学校生活をユーモラスに描く青春小説。
栄東(埼玉)、中央大学附属、豊島岡女子学園(どちらも東京)など
『給食アンサンブル2』(如月かずさ・著/光村図書出版)は章ごとに主人公をかえて展開する連作短編集。中学2年生の生活を給食にからめ、6人の視点で話が進みます。よく取り上げられたのが吹奏楽部の部長として改革に取り組もうとした結果、部員と対立した高城を主人公にした「クリームシチュー」の章。栄東(埼玉)と本郷(東京)は、高城が給食の保温食缶を運んでいるときにクリームシチューをこぼし、片づけを手伝う副部長とのやりとりを通して気持ちを切り替えるシーンから出題。最後の「新たな決意」を記述式で説明させました。
『給食アンサンブル2』
如月かずさ・著/光村図書出版
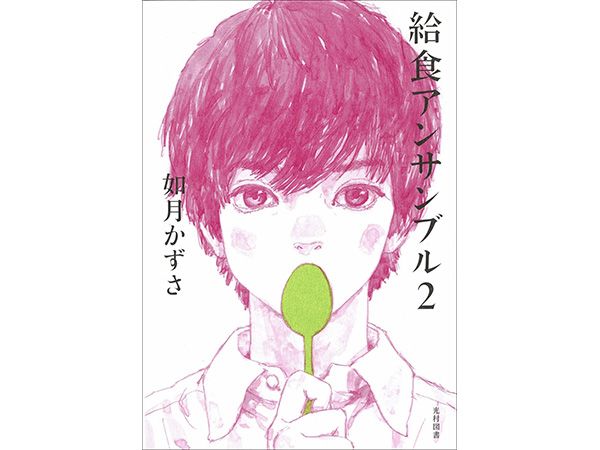
2020年度の入試でよく取り上げられた『給食アンサンブル』の続編。「アーモンドフィッシュ」「クリームシチュー」など給食のメニューで各章が構成され、中学2年生が成長する姿を描く。
栄東、春日部共栄(どちらも埼玉)、青山学院中等部、本郷(どちらも東京)、清風(大阪)など
『きみの話を聞かせてくれよ』(村上雅郁・著/フレーベル館)も連作短編集で、中学を舞台にした作品です。美術部の六花が、陸上部の早緑とけんかして気まずくなってから仲直りをするまでの話「シロクマを描いて」からの出題がめだちました。大妻(東京)や専修大学松戸(千葉)など仲直りのシーンを中心に取り上げた学校では、気持ちをあらわす表現に傍線を引いて具体的な内容を問い、学習院中等科(東京)では行動の理由を記述させたり、「らしい」という文末表現が用いられている理由を答えさせたりしました。また、駒場東邦(東京)では女らしさ、男らしさのイメージに苦しむ「タルトタタンの作り方」から出題。最後の設問では文章全体をふまえた生徒の会話文で、空欄に合う具体例を記述させました。
『きみの話を聞かせてくれよ』
村上雅郁・著/フレーベル館
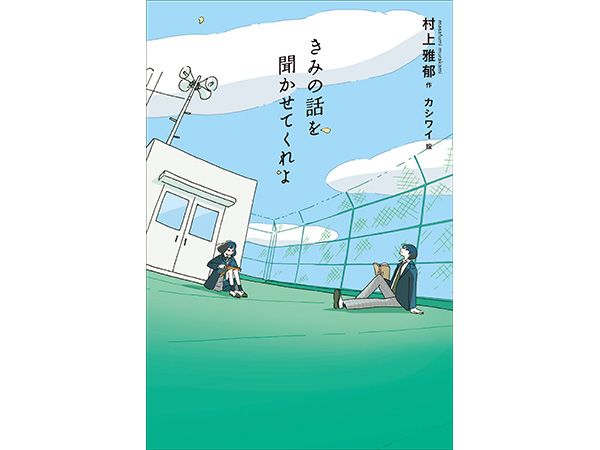
7人の中学生らが主人公の連作短編。「聞かせてくれよ」と登場する黒野良輔に悩みを打ち明け、7人の心は軽くなる。
栄東(埼玉)、専修大学松戸(千葉)、大妻、学習院中等科、駒場東邦(どれも東京)、日本女子大学附属(神奈川)など
『教室のゴルディロックスゾーン』(こざわたまこ・著/小学館)も連作短編集です。中学2年生のクラスメートの思いがすれちがうようすが主人公をかえて展開され、それぞれの事情が明らかになります。入試ではおもに心情の読み取りが問われました。南山中学女子部(愛知)は、トラブルをかかえた友達のようすを、集団のなかで凶暴化するバッタの相変異にたとえたうえで、自分たちを「バッタではない」という言葉にこめられた気持ちを100字以内で記述させました。
『教室のゴルディロックスゾーン』
こざわたまこ・著/小学館
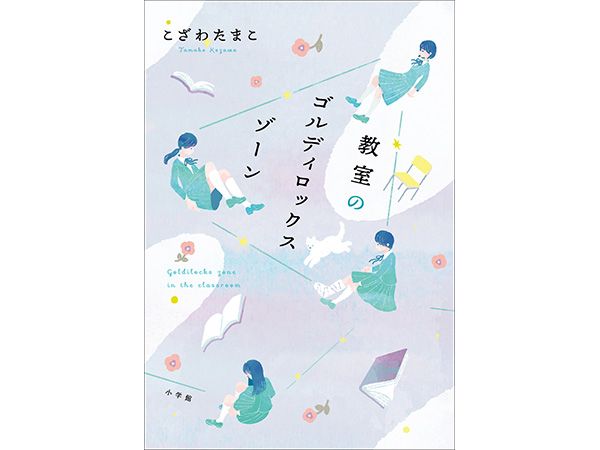
中学2年生の依子は内気な性格で、友達とのやりとりも不得手。心を開いていた飼い犬を亡くし、さみしさを妄想で紛らわすが、クラスメートとかかわりを深め、かわっていく。
栄東、西武学園文理(どちらも埼玉)、大妻(東京)、南山中学女子部(愛知)など
説明文 他者との関係性を問う題材に
説明文(論説文)は生物学を切り口にしたものをはじめ、言語学、ものの見方や考え方、人間関係、AI時代など、さまざまな分野が取り上げられました。
◇
その一つが『増えるものたちの進化生物学』(市橋伯一・著/ちくまプリマー新書)。生物学者である著者が「なんで生きているのだろう?」という疑問に対し、さまざまな角度から科学的に答えようとします。「なぜ生きているのか」「なぜ死にたくないのか」など五つの章で構成。入試では「なぜ他人が気になるのか」「何のために生まれてきたのか」からの出題がめだちました。
栄東(埼玉)では傍線部の理由や意味を読み取らせたうえで、最後の問いで生徒同士の会話を通して本文の内容を最も適切に踏まえた発言を選択。筑波大学附属(東京)では「なぜ他人が気になるのか」の一部に続けて、同じ著者による別の作品を示し、児童の話し合いを通して二つの文章を比較する出題もありました。このように話し合いに展開したり、複数の文章を比較したりする形は最近の高校入試や大学入学共通テストでもよくみられます。
『増えるものたちの進化生物学』
市橋伯一・著/ちくまプリマー新書

生物の進化が人間の生き方とどうつながっているのか――。こんな問いかけに、生物学者がさまざまな生物の例を出しながら答える。
栄東、春日部共栄(どちらも埼玉)、青山学院中等部、学習院中等科、筑波大学附属(どれも東京)など
『“正しい”を疑え!』(真山仁・著/岩波ジュニア新書)は、世間が正しいと思っていることを疑おう、というメッセージがこめられた作品。小説家である著者が、SNSにおけるコミュニケーションや新型コロナウイルスの影響による自粛などを例に挙げ、何事も決めつけず、本当にそうなのかと考える方法を伝えています。
入試では「コミュニケーション苦手解消法」「疑う力という武器を持て」「小説があなたを鍛える」などの章から出題。豊島岡女子学園(東京)は、ある発言にいだく違和感を深掘りする部分に空欄を設け、つながりに合う文を選ばせました。鷗友学園女子(東京)は大問2として出題。小説を読むことで登場人物に多様性があることが具体的にわかるという部分に傍線を引き、大問1の別の作品から、2人の登場人物の違いがあらわれたところを挙げて説明させました。これも複数の文章の読み取りに近い形かもしれません。
『“正しい”を疑え!』
真山仁・著/岩波ジュニア新書
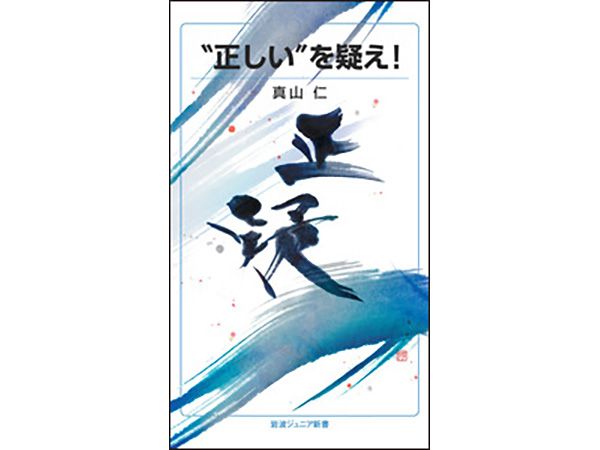
情報があふれる現代の社会では、何をよりどころにすればいいのか、経済を題材にした小説なども書く著者が親身に語りかける。
芝浦工業大学柏(千葉)、青山学院中等部、鷗友学園女子、豊島岡女子学園(どれも東京)など
『ものがわかるということ』(養老孟司・著/祥伝社)は解剖学者によるエッセー。入試では浅野(神奈川)が第1章を取り上げ、筆者の考える情報社会とは何かを選択させました。甲陽学院(兵庫)は、自然との共鳴について述べた章から、筆者のいう情報化と情報処理の違いを問いました。
『ものがわかるということ』
養老孟司・著/祥伝社
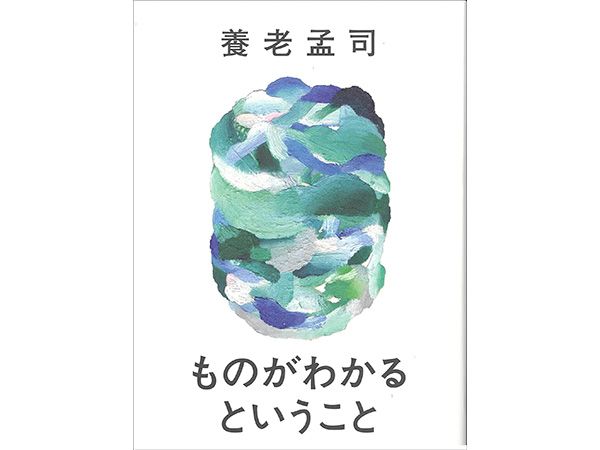
『バカの壁』などのベストセラーがある著者の生き方や人生観が伝わるエッセー。ものがわかるということ、世間や他人とどう付き合うかなどについて考えを語る。
芝浦工業大学柏(千葉)、浅野(神奈川)、甲陽学院(兵庫)など
『「利他」の生物学 適者生存を超える進化のドラマ』(鈴木正彦・末光隆志・著/中公新書)は植物学者と動物学者が大人向けに書いたものです。やや難しめの内容ですが、栄東(埼玉)や西武学園文理(埼玉)は前書きのような位置づけで、比較的読みやすい「序にかえて」を取り上げました。
『「利他」の生物学 適者生存を超える進化のドラマ』
鈴木正彦・末光隆志・著/中公新書
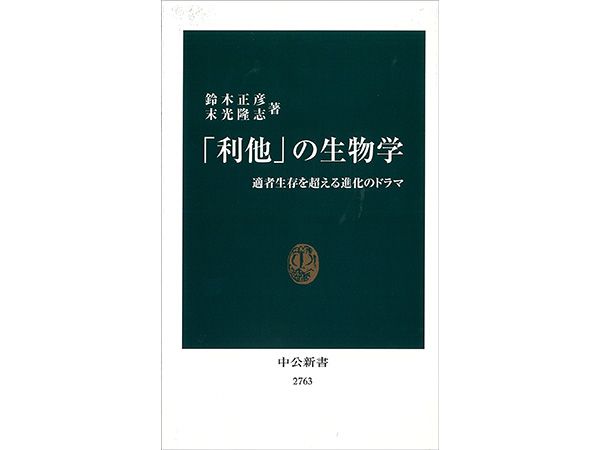
ある生き物がほかの生き物のメリットになる「利他的」な行動をとることについて、植物学者と動物学者が事例を挙げながら、わかりやすく解説する。
栄東、西武学園文理(どちらも埼玉)、大妻(東京)など
※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

開成・灘・渋幕・西大和の先生のコラムが読めるのは朝日小学生新聞だけ! 「朝小プラス」は中学入試の時事問題対策に強いと評判の朝日小学生新聞のデジタル版です。 読解力をアップして志望校合格を目指そう!




