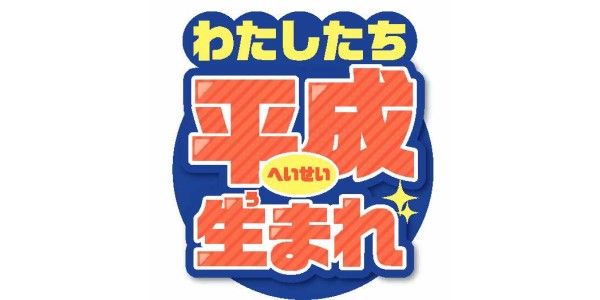
みなさんのクラスの時間割表は、月曜日から金曜日まででしょう。公立小学校で毎週土曜日が休みになったのは2002(平成14)年4月からでした。土曜日と日曜日が休みの「学校週5日制」は「平成生まれ」です。小学生の土曜日の過ごし方はどう変わってきたのでしょうか。朝日小学生新聞の紙面でふり返ります。(岩本尚子)
土曜休みを紙面でふり返る
月1「よかった」8割
公立小学校で月1回、土曜日が休みになったのは1992(平成4)年9月からでした。10か月後、93年6月の紙面に、朝小リポーターのアンケート結果を掲載しました。回答した54人のうち約8割にあたる41人が「休みになってよかった」としていました。家族や友だちと遊ぶ時間ができた、などが理由でした。

月2「よかった」6割
95(平成7)年4月には月2回、土曜日が休みになりました。同年6月に掲載した朝小リポーターのアンケートでは「よかった」と答えたのは49人中31人で、約6割に減りました。「どちらともいえない」が15人で、その理由は「習いごとがある」「休みだと友だちと会えない」「平日の授業が長くなった」などでした。

毎週「学力心配」8割
2002(平成14)年4月から、毎週土曜日が休みになりました。地域のスポーツチームの練習日になったり、地域や学習塾などがイベントや補習クラスを開いたりして、子どもたちには過ごし方の選択肢が増えました。
同時に、学習指導要領が大きく変わり、学校で勉強する内容が3割減る「ゆとり教育」が始まりました。読者の保護者107人が回答したアンケートでは、107人中90人が「学力の低下を心配したことがある」と答えていました。

「脱ゆとり」で授業復活
04(平成16)年12月、世界の子どもたちの学力をはかる調査で、日本の順位が下がったことがわかりました。当時の文部科学大臣が「土曜日に授業をしてもいい」という考えを示し、ゆとり教育の見直しが始まりました。
朝小読者は、土曜日が休みの生活リズムに慣れてきたころだったので、05年1月の紙面では「コロコロ変えないで」「実験台みたい」と不満の声もあげました。
11(平成23)年の学習指導要領改訂で、小学校の授業時間数は大きく増えました。夏休みを減らしたり、平日の授業をのばしたりするほか、土曜日に授業をする学校が増えました。
2020年の学習指導要領改訂でも、授業時間数は増えます。現在、土曜授業は「充実した学習機会を提供する方策」としておしすすめられています。

ふりこのようにゆれた政策
ベネッセ教育総合研究所の木村治生さんは、土曜授業がなくなったり、また始まったりしたのは、「日本の教育政策の流れと関連しています」と解説します。
1980年代は子どもの数が多く、受験競争がはげしかったため、子どもたちの「勉強のしすぎ」が問題になりました。知識をつめこむだけでなく、考えたり経験したりする「ゆとり」の時間をつくろうと、92年から10年かけて学校週5日制を実現させました。
その後、土曜授業は復活していますが、内容は学校の中にとどまらない「地域、社会に開かれた学び」が中心です。
知識を学ぶ系統学習と、知識を使って課題を解決する経験。どちらを優先するか、「日本の教育政策はふりこのようにゆれてきた」と木村さんは指摘します。そして、2020年からの学習指導要領は一方を優先せず、両方をとろうとするものです。
次の課題は、それを社会がどう支えるか。「土曜日ならではの学び」を実現させるため、学校や地域、企業などさまざまな人たちが力を合わせられるよう、しくみ作りが進んでいます。
(朝日小学生新聞2018年10月30日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。




