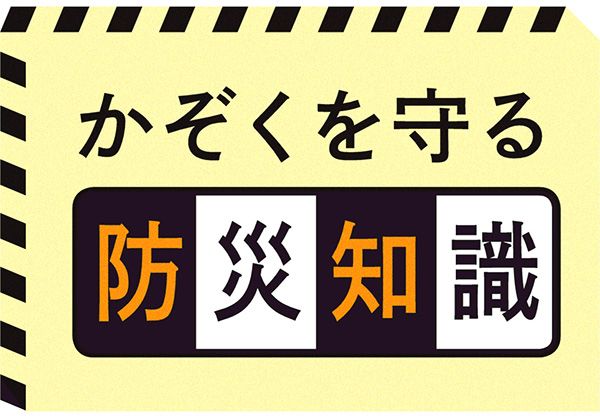
命の通り道
地震時行動に絶対はない
令和6年能登半島地震の発災1週間目の現場で見たのは、瓦屋根ごと押しつぶされたおびただしい家屋の残骸でした。この地震による犠牲者の多くは、家屋倒壊によるものです。同じ活断層型地震である阪神淡路大震災や熊本地震の際も、倒壊家屋の下敷きによる圧死が8割を超えています。
そこで重要になるのが地震直後の行動です。耐震性の高い鉄筋コンクリートの学校やマンションであれば「地震! 机の下へ」で良いのですが、耐震性が低い建物ではそれが正しいとは限りません。家がつぶれれば、机もつぶれる危険があるからです。とはいえ、一刻の猶予もない場合は机の下も当然ありで、それで助かった事例もあります。地震時の行動に絶対はなく、状況に合わせた臨機応変の対応が必要です
築年で変わる建物被害
「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」が、家屋被害は建築時期で左右されると報告しています。1981年5月31日以前の「旧耐震基準」で建築された家屋では、「全壊・大破」が45.7%、81年6月1日~2000年5月31日までの「新耐震基準」の家屋でも、「全壊・大破」が18.4%に上りますが、それ以降に建てられた「2000年基準」の家屋では「全壊・大破」は6%でした。
2000年の改正点は、「地盤に応じた基礎設計」「基礎と柱との接合部の金具取り付け」「耐力壁のバランスと配置」などの強化でした。その効果は熊本地震で如実に表れました。つまり木造家屋の場合、建築時期も地震時行動の目安にすべきです。
避難経路の確保
例えば、2000年基準以前に建てられた木造家屋の1階にいる時、小さな揺れを感じたり緊急地震速報が鳴ったりしたら、すぐに玄関ドアを開け、倒壊の危険があると思ったら直ちに外へ脱出します。2階にいたら、あわてて1階に降りない方がいい。つぶれても2階の方が隙間ができやすく助かる確率が高いのです。
2000年基準後の家でしたら、倒壊の危険性が低いので、すぐに外へ飛び出さず様子を見ます。ただ、ドアが変形し閉じ込められる恐れがありますので、玄関ドアを開け、閉じないようにして、命の通り道を確保します。
就寝中などで猶予がなければ、机の下やベッド横にうつ伏せになって揺れが収まるのを待ちます。それが空振りだったとしても、こうした安全行動の習慣付けが自分や家族の命を守るのです。

山村 武彦(やまむら たけひこ)
防災システム研究所所長。東京都出身。実践的防災・危機管理の第一人者。1964年、新潟 地震でのボランティア活動を契機に、研究所を設立。以来50年以上、世界中で発生する災害の現地調査を実施。報道番組での解説や講演、執筆活動などを通して防災意識の啓発に取り組む。企業や自治体の社外顧問やアドバイザーを歴任。防災・危機管理マニュアルの策定など、災害に強い街づくりに携わる。座右の銘は「真実と教訓は、現場にあり」。
(朝小かぞくの新聞2024年5月20日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。




