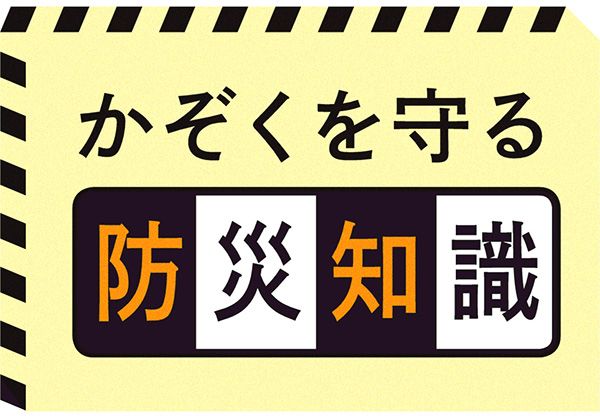
地震、大雨に備えた「防災大掃除」
命捨てるな、モノ捨てろ
近年発生した地震による負傷者の3~5割が、家具類の転倒・落下によるものです。また、その際火災が発生しても、家具類で扉が塞がれると逃げられなくなってしまいます。能登半島地震では、大津波警報の発表もあり、閉じ込められた人が長時間救出されず、低体温症で死亡した例もあります。
家の耐震化、家具類の転倒落下防止対策と同時に、お勧めするのが「防災大掃除」です。生活しているといつの間にかモノが増えていきます。ですから、家族で話し合って〇月〇日は全員参加の「防災大掃除の日」と決めるのです。不要なものは思い切ってリサイクルショップへ出すなどの断捨離です。自分や家族の命より大切なモノなど滅多にありません。
「我が家を安全シェルターに」が合言葉です。
子供目線で整理整頓
片づける際は重いものは下に、軽いものを上に置くよう心掛けます。例えば、阪神・淡路大震災の時、タンスの上に置いたコインの詰まった貯金箱(缶)が、寝ていた幼児の上に落下して大けがをさせたこともあります。また、テレビ台は大人の腰ほどの高さだったとしても、それは幼児の頭や目の高さになり、地震で倒れたり滑り落ちたりすればテレビも凶器になります。
大揺れをイメージして子供目線で設置場所の是非を考え、テレビと台を固定し、必要不可欠な片づけられないモノは、複数箇所で転倒防止対策をします。万一、家具が倒れても出入口が塞がれないように、発災時の動線を考え、より適切な配置を考えます。
目詰まり水害を防ぐ
大雨に備えた大掃除も大切です。昨今は河川の堤防決壊により引き起こされる外水氾濫よりも、排水能力を超えた集中豪雨で都市部が浸水してしまう内水氾濫が増えています。
その中には目詰まり水害があります。道路沿いの側溝にはグレーチングと呼ばれる格子状の鉄蓋がかぶせてあり、雨水はその格子状の網目から流れ落ち排水されます。しかし、そこが小石、泥、木の葉などで塞がれると排水不能となり、冠水・浸水で避難さえ困難になります。大雨が降る前に隣近所に声をかけ、側溝や排水口の清掃が必要です。
交通量の多い目詰まり箇所は道路管理者などに連絡します。また、行き場を失った雨水がサッシの隙間から室内に侵入しないように、ベランダの排水口の清掃、あわせて飛ばされそうなものの固定など屋内外を片づけておくと安心です。

山村 武彦(やまむら たけひこ)
防災システム研究所所長。東京都出身。実践的防災・危機管理の第一人者。1964年、新潟 地震でのボランティア活動を契機に、研究所を設立。以来50年以上、世界中で発生する災害の現地調査を実施。報道番組での解説や講演、執筆活動などを通して防災意識の啓発に取り組む。企業や自治体の社外顧問やアドバイザーを歴任。防災・危機管理マニュアルの策定など、災害に強い街づくりに携わる。座右の銘は「真実と教訓は、現場にあり」。
(朝小かぞくの新聞2024年7月20日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。




