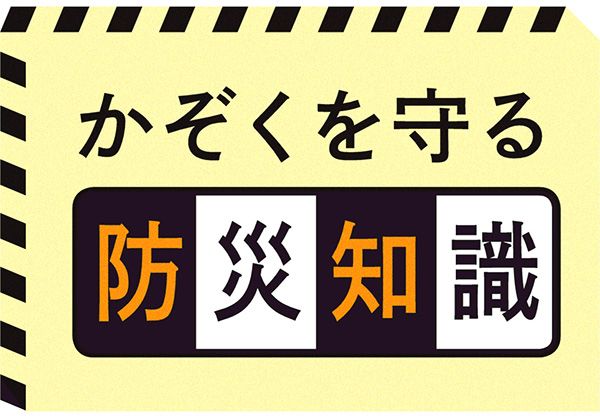
地震列島に住むマナー
大人の無知が招いた人災
死者6人負傷者462人の人的被害を出した2018年大阪府北部地震。震度6弱の揺れを観測した高槻市では、登校途中の当時小学4年生(9歳)の女児が、歩道に倒れてきたブロック塀の下敷きになり亡くなっています。
このブロック塀は小学校のプール沿いにあり、3年前に防災アドバイザーが危険と指摘したのですが、点検した教育委員会の職員は安全と判断し放置していたものです。私は翌日現地で見ましたが、ブロック塀の高さ制限2.2メートルをはるかに超える3.5メートルもあり、2.2メートル以上のものに必要な倒壊防止用「控え壁」も未設置で、適切な鉄筋も入っていませんでした。誰が見ても建築基準法違反は明らかです。
その後、高槻市ではブロック塀からフェンスへの転換をすすめ、「小中学校分は22年度に、幼稚園や公民館は28年度までに完了予定」としています。
6,700万円の賠償請求
大阪市東淀川区でも、その地震で通学路交通安全ボランティアだった80歳の男性が見守りに行く途中、民家のブロック塀崩壊で死亡しています。
1978年の宮城県沖地震では、死者28人のうち16人がブロック塀や門柱の倒壊によるもの。地震後、建築基準法が改正され、建物の耐震基準と共にブロック塀の安全基準が強化され、ブロック塀は生垣に変えるべきとの声が高まりました。自治体も助成金を付け改修推進を図りましたが、時間と共に風化し、同じような事故は今も地震のたびに起きています。16年の熊本地震ではブロック塀の崩壊で29歳の若者が死亡、遺族らが所有者に6,700万円の損害賠償を請求する訴訟を起こしています。
安全対策はマナー
地震で塀や門柱が崩壊すれば、家族だけでなく通行人をも犠牲にします。自分が加害者にならないためにも、今のうちに耐震性の低いブロック塀は生垣などに変えることをお勧めします。
今では熱と圧力を加えた圧縮木材を使った風情のある木塀も多くみられるようになりました。処理された圧縮木材は一定の耐水・難燃性があり、持続可能な森林資源活用としても期待されています。我が家の安全対策は地震列島に住む者のマナーでもあります。
この機会に、お子さんと一緒に通園・通学路を歩いてみてください。危険な崖、ブロック塀・看板・瓦・自動販売機など転倒落下物の有無、地震時は危険なものから離れる安全の知識と行動を共有しておきたいものです。

山村 武彦(やまむら たけひこ)
防災システム研究所所長。東京都出身。実践的防災・危機管理の第一人者。1964年、新潟 地震でのボランティア活動を契機に、研究所を設立。以来50年以上、世界中で発生する災害の現地調査を実施。報道番組での解説や講演、執筆活動などを通して防災意識の啓発に取り組む。企業や自治体の社外顧問やアドバイザーを歴任。防災・危機管理マニュアルの策定など、災害に強い街づくりに携わる。座右の銘は「真実と教訓は、現場にあり」。
(朝小かぞくの新聞2024年9月20日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。




