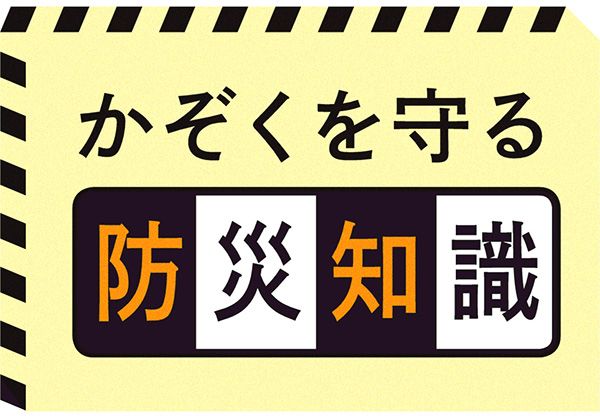
旧耐震基準と新耐震基準
令和6年能登半島地震の犠牲者の多くが、建物の倒壊によるものでした。地震に強いか弱いかは、建物の耐震性能に左右されます。建物が地震の揺れに耐え、倒壊・崩壊しない性能を定めたものを「耐震基準」といいます。1981年5月31日以前が「旧耐震基準」で、「震度5強程度の中規模地震に対して、建物が倒壊・崩壊しない」ことが目安でした。つまり、震度6弱以上の大揺れでは旧耐震基準の建物は、倒壊・崩壊の危険があるのです。
1981年6月1日以降が「新耐震基準」で、「震度5強程度の中規模地震に対して建物がほとんど損傷せず、震度6強~震度7程度の大規模地震に対して建物が倒壊・崩壊しない、または多少の損傷は許容」となっていましたが、絶対安全ではありませんでした。
熊本地震後の木造建物調査で、旧耐震基準の建物は全壊・大破が45.7パーセント、新耐震基準の建物でも全壊・大破が18.4パーセントに上ったのです。
2000年基準の建物は強かった
2000年6月1日以降の基準は「2000年基準」と呼ばれ、従来の耐震性能に加え、「地盤に応じた基礎設計」「基礎と柱の接合部に金具の取り付け」「耐震壁のバランスと配置」が強化されました。その結果、前述の調査で2000年基準の建物の全壊・大破は6%に過ぎず、被害なしが圧倒的多数を占め、耐震性能の高さが証明されたのです。
もし、ご自宅が2000年5月31日以前に建築された木造建物なら、耐震性能が懸念されますので、耐震診断を行い必要であれば耐震改修をお勧めします。耐震診断や耐震改修には助成措置がありますので自治体に相談されると良いと思います。
耐震シェルター
しかし、個人負担などもあり耐震改修を躊躇される方には、建物全体を改修するのではなく一部屋だけ鉄骨を組み、建物が倒壊してもその部屋に退避すれば命を守ることができる「耐震シェルター」を設置する方法もあります。
また、普通のテーブルだと家がつぶれればテーブルもつぶれてしまいますが「耐震テーブル」は耐震性が高く、テーブルの下に身を隠せば、建物が倒壊しても命を守ることができます。さらに「防災ベッド」や「ベッド用耐震フレーム」もありますし、こうした耐震用品の購入にも助成金を出している自治体もあります。
日本中、いつでもどこでも大地震発生のおそれがあります。今のうちにわが家を地震に強い家にする努力が大切です。

山村 武彦(やまむら たけひこ)
防災システム研究所所長。東京都出身。実践的防災・危機管理の第一人者。1964年、新潟 地震でのボランティア活動を契機に、研究所を設立。以来50年以上、世界中で発生する災害の現地調査を実施。報道番組での解説や講演、執筆活動などを通して防災意識の啓発に取り組む。企業や自治体の社外顧問やアドバイザーを歴任。防災・危機管理マニュアルの策定など、災害に強い街づくりに携わる。座右の銘は「真実と教訓は、現場にあり」。
(朝小かぞくの新聞2024年11月20日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。




