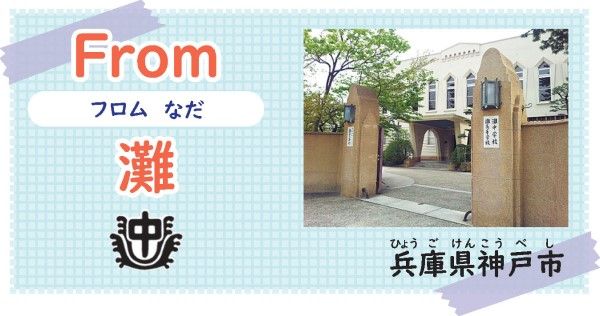
【国語編】☆From 灘
情景と気持ち 「掛詞」で奥深く
おもに平安時代や鎌倉時代、貴族を中心に、ふだんからたくさんの和歌がよまれました。それにともない、和歌の表現方法もおおいに発達しました。
その一つが「掛詞(かけことば)」です。同じ読み方で意味が異なる「同音異義」を使って、一つのことばに二つの意味を持たせます。和歌は五七五七七をあわせた31音が定型ですが、掛詞を使うとより多くの内容をあらわすことができます。
たとえば鎌倉時代にできた『新古今和歌集』という歌集には、相模という女性の歌人がよんだ「色かはる萩の下葉をみてもまづ人の心のあきぞ知らるる」という歌がおさめられています。「あき」が季節の「秋」とあきるという意味の「あき」の掛詞で、意味は「秋が来て根元に近い方から萩の葉の色が変わっているのを見てもまず、あなたの心に私へのあきがきて、愛情がうすれたことがわかってしまいます」となります。
掛詞の重要な役割の一つは、情景やものと、人の心や行動を重ね合わせることです。相模の歌では秋の情景とあきる気持ちが重ね合わせられて、「秋が来て色が変わる萩の葉」に「あなたの心変わり」がたとえられているのです。
かるた遊びなどでもなじみがある『小倉百人一首』にも、掛詞を用いた歌が多く選ばれています。お正月などに遊ぶ機会があれば、どの歌にどのような掛詞が用いられているかを解説書などで確認しながら読んでみてください。和歌という短い形式の詩の中で、歌人たちが目指した奥深い表現が味わえると思いますよ。

■灘中学・高校 国語科教諭 槇野祐大
(朝日小学生新聞2023年11月10日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。中学受験に役立つ記事「出るかも!時事問題」→「From灘」→「From渋谷幕張」→「From西大和→From開成」の順で掲載中です!




