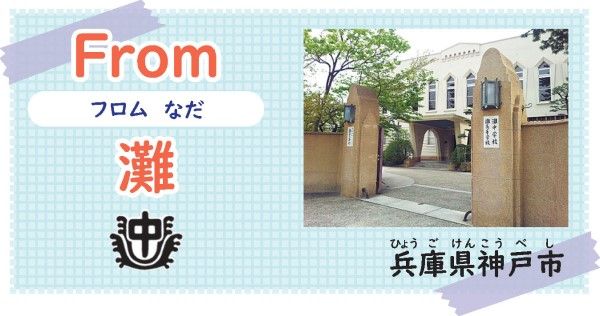
【国語編】☆From 灘
厳しい暑さが続いています。冷房を使ったり、こまめに水分補給をしたりして、熱中症を予防しましょう。
さて、平安時代の人々も夏の暑さにはなやまされていたようで、夏の終わりごろによまれた和歌の多くには「待ち遠しかった秋がようやく近づいてきた」という思いがにじみ出ています。
春から秋にかけてさく「なでしこ」は、平安時代には夏の花であるとみなされていました。「なでしこの花散りがたになりにけりわが待つ秋ぞ近くなるらし」、つまり「なでしこの花が散りかかっているなあ。私が待っている秋が近くなっているらしい」という和歌もあるほどです。春の終わりには散りゆく桜と過ぎゆく春をおしんだ和歌が数多く残されていることと比べると、春と夏のあつかいには大きな落差があるとわかります。
和歌のテーマの一つ「更衣」でも、夏の初めに薄着にかえる衣がえだけをよみ、秋や冬に向けたものはよみません。更衣をよんだ和歌の内容をくわしく見るとやはり、暑い夏を少しでも涼しく乗り切ろうとした人々の心が見えてきます。
平安時代の貴族が着た夏用の衣服は肌の色がすけるほど薄かったようです。しかし貴族の女性が書いた「枕草子」という随筆には、夏にはその衣服1枚さえ暑苦しく感じると書かれており、やはり暑さはたえがたかったようです。加えて政務や儀式といった仕事の時に着るように決められた衣服は、何枚も重ね着をするものでした。さぞかし暑かったろうな、と同情せずにはいられません。
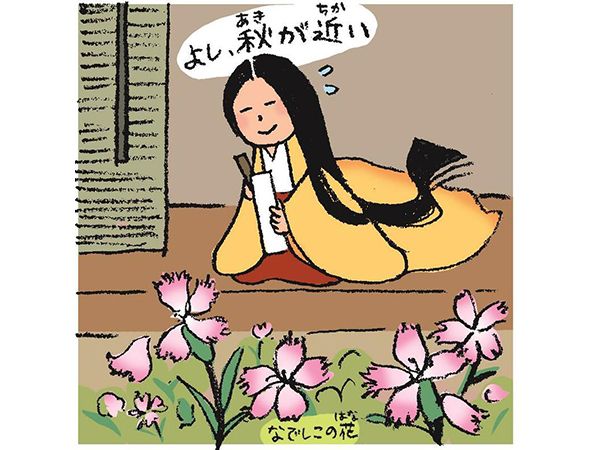
灘中学・高校(兵庫県神戸市)
国語科教諭 槇野祐大
(朝日小学生新聞2023年7月28日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。中学受験に役立つ記事「出るかも!時事問題」→「From灘」→「From渋谷幕張」→「From西大和→From開成」の順で掲載中です!




