
2024年度の中学入試では、国語でどのような文章が出題されたのでしょうか。朝小の編集部は各地の中学から入試問題を入手し、よく取り上げられた作品を調べました。前回、のせきれなかったものを今回、追加で紹介します。(山本朝子)
入試に出る本は、前年の秋までに出版された新しいものがめだちます。一方、前年の入試で使われた作品が、翌年以降の別の学校の入試で使われることもあります。今年出たからもう出ない、ではなく、興味を持てる本があれば、目を通しておいてもいいかもしれません。
◇
物語文は、いまの小学生や中学生の気持ちをえがいた作品が多いなか、2024年1月に直木賞を受賞して話題になった『八月の御所グラウンド』(万城目学・著/文芸春秋)もありました。大人向けの作品でも、登場人物が10代で読みやすいものがあれば、子どもはもちろん、保護者も読むと、親子の会話がはずむのではないでしょうか。
出版社の児童文学賞を受賞した作品もよく出ます。主人公の成長をえがくなかで、いじめや貧困など読み手の胸が痛くなるような場面もあります。「おもしろい」本とはいえないかもしれませんが、そうした困難に立ち向かう登場人物の気持ちを感じ取る力や想像力が育まれ、今後の生き方を考える機会にもなる可能性があります。
◇
『リカバリー・カバヒコ』(青山美智子・著/光文社)はある新築マンションにかかわる人たちを章ごとに異なる主人公にした連作短編です。
芝(東京)や甲陽学院(兵庫)は「勇哉の足」から出題。新築マンションに住む4年生の勇哉が、駅伝の選手に選ばれたくないためにうそをついてしまってからの気持ちの変化を問いました。
『リカバリー・カバヒコ』
青山美智子・著/光文社

公園にある古ぼけたカバの遊具は、自分の治したい部分と同じ部分をさわると回復するといわれている。カバに悩みを打ち明け、前を向く人たちの物語。
芝(東京)、甲陽学院(兵庫)など
『おくることば』(重松清・著/新潮文庫)からは短編「反抗期」が取り上げられました。
学習院中等科(東京)は、新型コロナウイルスの病気の分類がかわるのを前に、卒業式はマスクをつけないことが基本になったため、マスクをどうするか、主人公の少年が同級生の女子と話す場面を読ませ、恥ずかしくなった気持ちなどを問いました。関西学院中学部(兵庫)は、友だちが同居の祖母を気づかってマスクを外せないことを知って気持ちがゆれ動く場面を取り上げました。
『おくることば』
重松清・著/新潮文庫
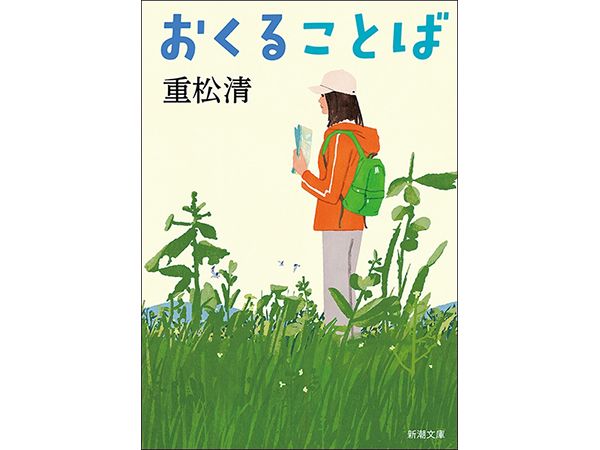
短編「反抗期」は感染予防のために強いられたマスク生活にあらがう6年生の日々をリアルにあらわす。
学習院中等科(東京)、関西学院中学部(兵庫)など
『この夏の星を見る』(辻村深月・著/KADOKAWA)は新型コロナウイルスが流行して学校が休校になった2020年の春からの1年あまりをえがいた作品です。
学習院女子中等科(東京)は、休校中に友だちと会えずにいる高2の女子の気持ちを、神戸女学院中学部(兵庫)は、学校が再開されてからのとまどいを、それぞれ読み取らせました。
『この夏の星を見る』
辻村深月・著/KADOKAWA
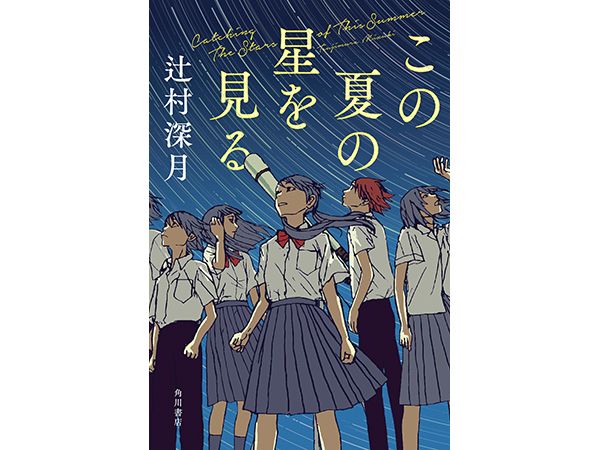
コロナ禍で休校や部活動の制限にみまわれた中高生が、困難と向き合いながら天体の観測を通してつながり、交流する。
学習院女子中等科(東京)、神戸女学院中学部(兵庫)など
『きみの鐘が鳴る』(尾崎英子・著/ポプラ社)は、同じ塾に通い、中学受験にいどむ男女4人を主人公にした物語です。
学習院女子中等科(東京)は、空の描写の変化から作者があらわそうとしていることを問いました。芝(東京)は、併願校が不合格でショックを受ける場面から、図形の補助線になぞらえた登場人物の本心について記述させました。
『お菓子の船』(上野歩・著/講談社)は、菓子職人の話です。菓子職人だった祖父のどら焼きの味が忘れられず、菓子職人をめざすことになった20歳のワコが苦労しながら理想の味に近づこうとします。
鷗友学園女子(東京)と城北(東京)は、どちらも同じ部分から出題。鷗友はワコにうそをついた仕事仲間の小原が目尻に涙をにじませる部分に傍線を引き、心情の変化を記述させました。城北(東京)は最後の設問で、ある中学の生徒同士の話し合いという設定で、ワコのその後を予想させました。このように話し合いに展開する形は最近の高校入試や大学入学共通テストでもよくみられます。
『お菓子の船』
上野歩・著/講談社
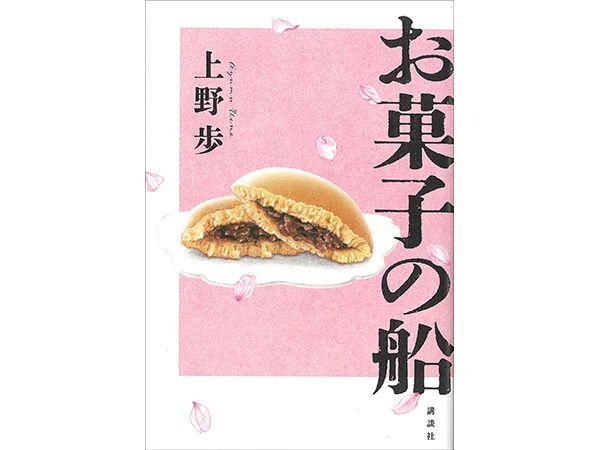
太平洋戦争中に食料を補給する船でお菓子をつくっていた亡き祖父。その味を追い求めて菓子職人になった孫娘を通して、過去と現在を行き来しながら進む物語。
鷗友学園女子、城北(どちらも東京)など
『街に躍ねる』(川上佐都・著/ポプラ社)は、他人とのコミュニケーションが苦手で不登校の兄と、兄が大好きな弟が、世間の目に傷つきながら成長する物語。
滝(愛知)は、兄に「ふつう」であることを求めてしまう弟の心の内を選択させました。愛光(愛媛)は、弟が学校でいやな気持ちになったことを兄に聞いてもらったときの気持ちを選ばせました。
『街に躍ねる』
川上佐都・著/ポプラ社
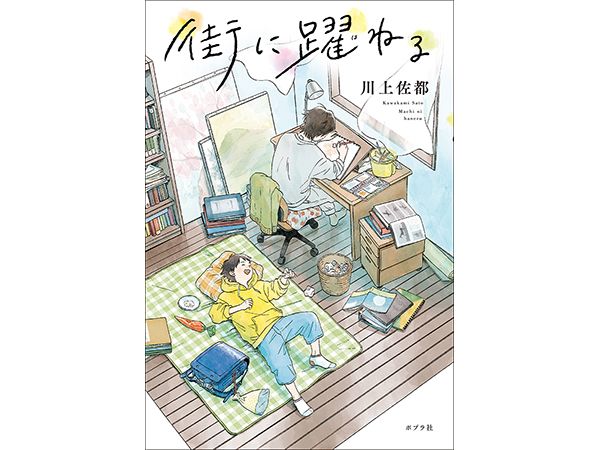
5年生と高校生の兄弟。大好きな兄が「ふつうじゃない」ことに気づき、とまどいながら現実と向き合う姿がいとおしい物語。
滝(愛知)、愛光(愛媛)など
『八月の御所グラウンド』(万城目学・著/文芸春秋)には二つの作品が収められています。表題作は野球の話。もう一つの「十二月の都大路上下ル」は京都でおこなわれる女子全国高校駅伝の話で、補欠だったのに当日、急に選手として走ることになった高校1年生の坂東が主人公です。
ともに坂東がたすきを受け取るまでのシーンを切り取った学校のうち、西武学園文理(埼玉)は緊張が高まるようすを比喩を用いてあらわした部分に傍線を引き、適切な説明を選ばせました。筑波大学附属(東京)は最後の設問で、表現の工夫について小学生同士の話し合いを読ませ、空欄に合う文中の語句を書きぬかせました。
◇
説明文(論説文)では哲学にかんするものが毎年、出されます。『SNSの哲学 リアルとオンラインのあいだ』(戸谷洋志・著/創元社)は哲学者の著者が身近なSNSを題材に、インスタグラムなどのSNSを使っているときの読者自身について問いかけながら人間やSNSの性質を解き明かす本です。SNSで、もやもやしたことがある大人にも気づきをあたえてくれそうです。巻末には各章の内容に関連する作品案内もあります。
淑徳与野(埼玉)は「なぜSNSで承認されたいのか」という章を取り上げ、承認(投稿に「いいね」などを得ること)欲求について読み取らせました。芝(東京)は「SNSで人は連帯できるのか」という最終章から出題。SNSを活用しておこなわれる政治的な活動のために必要なことを100字以内で説明させました。
『SNSの哲学 リアルとオンラインのあいだ』
戸谷洋志・著/創元社
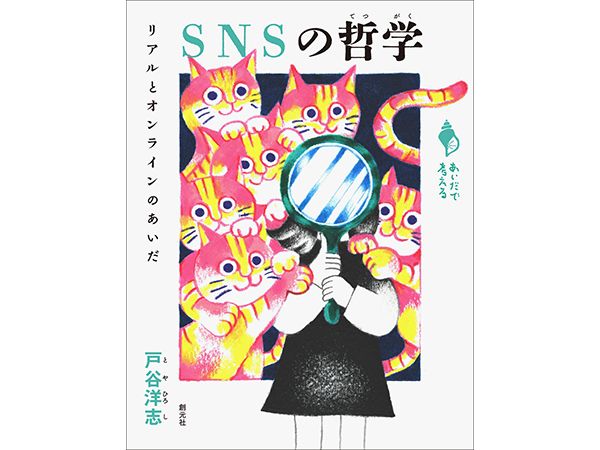
「SNS疲れ」「つぶやきと炎上」「政治に利用されるSNS」などを通して、SNSについて哲学的に考える。
淑徳与野(埼玉)、芝(東京)など
※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。

開成・灘・渋幕・西大和の先生のコラムが読めるのは朝日小学生新聞だけ! 「朝小プラス」は中学入試の時事問題対策に強いと評判の朝日小学生新聞のデジタル版です。 読解力をアップして志望校合格を目指そう!







