隊員の4~6年生11人 テーマをそれぞれ発表
さかなクンといっしょに、子どもたちが海や魚を調べて深める「さかなクン探究隊」の活動が、22日から始まりました。初回は隊員の小学生がそれぞれの研究テーマを発表。「すギョくわくわくします」とさかなクンは期待を寄せていました。(小貫友里)

「魚の中にどれくらいプラスチックが残っているのだろう?」「同じ魚なのに味や食感がちがうのはなぜなの?」「江の島の環境を水槽に再現してみたい」――。
東京海洋大学(東京都港区)で9月22日、青い地球を育む会が主催する「さかなクン探究隊」に参加する小学4~6年生の隊員11人が、それぞれの研究テーマを発表しあいました。隊員は朝小の告知などを見た応募者から、審査を経て選ばれました。
隊員は今後、海や魚に関係したテーマについて研究し、2025年2月に発表します。それだけでなく、さかなクンといっしょに海岸のごみひろいをしたり、海の専門家から最新の研究を教えてもらったりもします。
子どもたちの知りたい気持ちや、環境を守りたい気持ちを応援するこの活動は、さかなクンの「みんなの宝物である大自然の中で、自分が興味をもった物事について、感動いっぱいの調査にレッツ・ギョー!! 未来につないでいきましょう」という思いをもとに始まりました。隊員の発表を聞いたさかなクンは「すギョく堂々とした姿に感動」「これからのギョ活動にわくわくします」と、どの発表にも感動していました。
研究のおもしろさについて東京海洋大学学長の井関俊夫さんは、「自分なりに答えを探し出して、実験や観察をして正しいことを証明し、人に理解してもらうところまでたどり着くと、とっても気持ちがいいです。ぜひみなさんにその楽しみを味わってほしい」と話しました。

大学教授たちが応援
探究活動へのアドバイス
10月以降に隊員向けの講座を開く、東京海洋大学教授の内田圭一さんと清水悦郎さんは、「(その研究は)何匹くらい調べるの?」などと具体的な研究方法のアドバイスをしたり、「報告会が非常に楽しみ」と期待を寄せたりしていました。
(研究とは)思い通りの結果ではなくても、それが答えだと思うんです。ぜひ正直に、楽しみながらめげずにがんばってください。
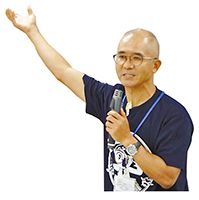
調べるうちにテーマの他にも「調べなきゃ」と思うことが出てくるかもしれないけれど、それも大切にしてほしい。もっとおもしろそうと思うものがあったら遠慮せず、自分が関心を持ったものを調べてもらえたら。

自然の中で見て、聞いて、ふれて、かおりをかいで、味わって。自分のギョ感(五感)で体感した学び、喜び、感動に勝るものはギョざいません。探究心を大きくするためにも、自然の中でギョ感をフルに使って。いつの日か大きなギョ発表をされることを、とっても楽しみにしています。

※朝小では今後、さかなクン探究隊の活動をシリーズで紹介します。さかなクン探究隊への申しこみは終了しています
(朝日小学生新聞2024年9月28日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。




