
累計発行部数7万部突破「たくや式」英語問題集シリーズの著者・藤井拓哉さんが、家族でのアメリカ生活や家庭での英語学習についてつづります。
バイリンガル教育は幼いうちが勝負!
個人的に「バイリンガル教育は幼いうちが勝負!」と考えている。その理由は、カタカナ英語から脱却できるかどうかの分かれ道になるから……というのも挙げられるが、実はそこではない。主な理由は「幼稚園・小学校に入ると本格的な日本語ワールドが襲来してくるから」だ。一般的な幼稚園・小学校は、基本日本語オンリーの世界だ。子どもも先生も「おはようございます」から「さようなら」まで、ずっと日本語。英語といったら、週に数回行われる英語のレッスンのみ。たとえ「家庭内では英語」とバイリンガル教育を続けていても「1日の半分以上が日本語」という環境では、英語力を伸ばすのは難しくなってくる。
そんなこともあり、たくや式バイリンガル教育は幼稚園に入る前からスタートさせていた。しかし「それじゃあ、小学校から始めたら遅すぎるの?」と言ったらそんなことは全くない!
むしろバイリンガルになる可能性は、かなりある。実際、小学生、更に中学生になってから本格的に英語学習を始め「え?帰国子女じゃないの?」と思わせる英語力を身につけたお子さんたちを私はたくさん見てきた。しかし、彼らのほとんどは「毎日オンラインレッスンを受けた」「英語の本を日本語の本より読んだ」「小学3年生で『たくや式中学英語ノート』10巻全て終わらせた」など、英語学習に対するコミットメントはかなり高いものだった。うちの子どもたちにそれができるか……と考えると正直自信がなかったため、私は「バイリンガル教育は幼稚園までに土台を作ろう!」と決めていた。
バイリンガル教育の第一ゴールは「発音」!
それでは幼いうちに何を身につけさせるべきか? それはズバリ「発音」! ここで想像してほしい。「あ、この人、英語ができる!」と思う人は、いったいどういう人だろう? 英字新聞を日頃から読んでいる人? TOEIC で高得点を取っている人? 確かにそういう人たちもすごいが、英語を流暢に話せる人を見た時の方が「うわ! この人、ヤバ!」と思うのではないだろうか?
何が言いたいか? それは、発音が良いだけで「英語ができる人」認定される場合があり、発音マジックが存在しているということだ。だからこそ「英語を自分の武器にしたい!」と思うのであれば、「カタカナ英語からの脱却(=発音をネイティブに近づける)」というのをまずは目指すべきなのである。
しかし、カタカナ英語脱却には少し厄介な点が……。そう、それは年齢が上がれば上がるほど脱却が難しくなるということである。もちろん大人になってから英語を本格的に学び、ネイティブ並みの発音をマスターしている人も少なからずいる。しかし、やはり幼い時の吸収率の方が桁違いに高い。そのため、たくや式バイリンガル教育では「発音強化」を中心に行なっていた。

発音を強化するために、まずはリスニングから
第2回でも述べたが、私がバイリンガル教育で実施したメソッドは以下の4つである。
メソッド1: 基本的に子どもが視聴するのは、英語のDVDやYouTube
メソッド2: 家や車で聴くのは、英語の歌
メソッド3: 本の読み聞かせも、英語と日本語
メソッド4: 父親が話しかける時は基本的に英語、母親が話しかける時は日本語
これらのメソッドは、基本的に「リスニング重視」となっている。「正しい発音をするにはまず正しい発音を聴き取れないといけないから」という理由から。また「英語=勉強」と捉えさせないようにするため「発音の練習をさせる」というより「自然と英語が口から出る環境作り」を心がけたからである。
それでは具体的に何を行ったのか、結果はどうだったのか、説明していこう。
メソッド1: 基本的に子供が視聴するのは、英語のDVDやYouTube
「英語が日常的にある環境(自然と英語が口から出る環境)」を作るため、ベタではあるが、テレビで流すのは「機関車トーマス」「パウ・パトロール」「チャギントン」、そしてDVDはディズニー映画をヘビロテ状態で見せていた。また、時々使うYouTubeではBaby Sharkを中心にキッズ向けの動画を見せていた。親戚や友だちの家に行けば、高確率で日本の番組が大画面で出迎えてくるので、せめて自宅のテレビは英語オンリーにしていた。(子どもたちには「うちのテレビは、なぜか知らないけど英語の番組しか映らないんだよね〜」と話していた)。
最近では、NetFlix や Amazon Prime などストリーミングサービスが豊富にあり、子ども向けの英語番組も多い。これらを使わない手はないだろう。ちなみに藤井家がアメリカに引っ越したばかりの頃は、Bluey、Spidey and His Amazing Friends、 Miraculous といった日本ではあまり馴染みのないアニメを子どもたちは見ていた。
メソッド2:家や車で聴くのは、英語の歌
家や車で聴く音楽も基本的に英語の歌であった。ただし「子ども向けオンリー」ではなく、親が聴いていて苦にならないTaylor Swift、Justin Bieber といったポップな曲や、クラシックやジャズなども流しており、どちらかというと「日本語の歌ではない曲」を流していた。ドライブ中に突然、機関車トーマスの主題歌が流れたと思ったら次に「We Are Never Ever Getting Back Together」が流れ、家では夕食後にジャズが流れるなど、バリエーション豊かな音楽生活となっていた。

メソッド3:本の読み聞かせも、英語と日本語
私がよく読んだのは、「Brown Bear, Brown Bear, What do you see?」 、「Five Little Monkeys」、「The Very Hungry Caterpillar」など。いずれも簡単なストーリーで、繰り返しのフレーズも登場するため、子どもたちが自然に真似してくれることもあった。特に 「Five Little Monkeys」 は大ヒット! 読み聞かせをした後、YouTubeで歌を流すと子どもたちは一緒に歌ったり踊ったりして大盛り上がりであった。
また、ディズニーの Dream Switch というプロジェクターも活用していた。多少高額ではあったものの、寝る前にお手軽に英語の読み聞かせをしてくれ、「疲れている中での絵本タイム」のプレッシャーから解放してくれる神アイテムであった。
そんな苦労もあり、読み聞かせのおかげでうちの子どもたちの英語力は飛躍的に伸びた……と言いたいところだが、言ってしまうと読み聞かせの成果は……あったのかな? 確かに子どもたちは幼稚園に入る前にアルファベットくらいは読めるようになったのだが、単語は全く……(泣)正直なところ、「英語を楽しいもの」と感じてもらうくらいの効果に留まったため、うちでは、あまり無理して行う必要もなかったのかもしれない。
メソッド4: 父親が話しかける時は基本的に英語、母親が話しかける時は日本語
たくや式バイリンガル教育の真髄、それは 「お父さんは英語しか話せないふり作戦」! そのため、私は子どもたちには、 ほぼ100%英語で話しかけていた。しかし、油断した時に「え? マジで?」などうっかり日本語がポロッと出たり、親戚や近所付き合いの際に日本語で話す場面が増えてしまったりで、案の定、かなり早い段階でミッション失敗となってしまった(泣)。そこで「パパは日本語も話せるけど英語の方が得意」という設定に切り替え。このことにより「パパ、それやめて」と言われることはなかったが、子どもたちが私に話しかける時は97%以上(Yes/No/OK や What?/Why? といった一言以外)が日本語となってしまった。
このメソッドは、最初のうちは子どもの英語力を刺激する良い方法であったが、ふとした時にキャラクター設定を忘れたり、子どもが思ったほど英語で返してくれなかったりと色々な意味で難しいメソッドであった。
発音強化はミッションコンプリート!
たくや式バイリンガル教育は、幼稚園に入って1か月ほどで徐々にフェイドアウトしていった。やはり、周りが日本人ばかりだったので仕方がないかと……。しかし、その後も私が子どもたちに話しかけるときは「英語50%、日本語50%」といった形で続けていた。(というより、基本的に英語で子育てをしてきたため、日本語で話しかけることが恥ずかしかったり違和感があったりで、気づいたら英語を話していた)。
そして現在、子どもたちの英語の「発音」は同じ学校に通っているアメリカ人の発音にかなり近い。また、学校にも嫌がらず通ってくれている。「え、子どもたちがアメリカに行ったのは6歳と9歳の時なんでしょ?それだけ幼い時に行っているんだから発音も良くて学校も嫌がらないのは当たり前でしょ?」と言われてしまうと何も言い返せないのだが、当時苦労したことを考えると、たくや式バイリンガル教育のおかげで英語を身近に感じることができ、発音強化にも少しは役に立ったと願いたい。
ということで「発音」に関しては、たくや式バイリンガル教育、堂々のミッションコンプリート! もちろん、完璧とは言えないが、子どもたちが先生や友だちと英語で会話をしている姿を見ていると「まあ、うちの子どもにしては上出来だな」と、しみじみ感じてしまう。
親も子どもも無理をしないこと
「結局、4つのメソッドのうちどれが一番ためになったのか?」と聞かれると正直困ってしまう。数値化して図ることができないため、答えは不明……としか言いようがない。しかし、「バイリンガル教育で最も重要なことは?」と問われたら、これは迷わず答えられる。「親も子どもも無理をしないこと」だと。
家庭というのは、何よりも「落ち着ける場所」でなくてはならない。家の外では、子どもも親も、たくさんの問題に直面し、時にはストレスを感じることがあるため、家庭内ではリラックスできる環境を整えるべきである。これは、親だけでなく子どもにとっても同じ。もし、バイリンガル教育を頑張りすぎた結果、家の中でもストレスがかかるようになってしまうのなら、それは本末転倒。そのため時々は「一緒にイッテQ を見る」「英語の読み聞かせをスキップ」「一緒にアニソンを歌う」というのもありだろう。ポイントは、「楽しめるバイリンガル教育」を目指すことである。
藤井拓哉(ふじい・たくや)

1984年生まれ。父親の都合で3歳~6歳までと、15歳~24歳までをアメリカのオハイオ州で過ごす。オハイオ州立大学、同大学院で教育学を学び、日本語の教員免許とTESOL(英語を母国語としない方のための英語教授法)を取得。帰国後は、宇都宮大学で英語講師を務める。数学、化学、生物学、物理学を英語で学ぶ「理数系英語」の講義を定期的に行い、2010年と2013年に学生による「授業評価アンケート」をもとに選ぶ「ベストレクチャー賞」を受賞。その後、上智大学、筑波大学などで英語講師を務めた後、2023年から家族でアメリカ暮らしを始める。著書に『たくや式中学英語ノート』シリーズ(朝日学生新聞社)、『MP3CD付き ガチトレ 英語スピーキング徹底トレーニング』シリーズ(ベレ出版)。TOEIC955点、TOEFL101点。
「たくや式中学英語ノート」全10巻
【著者によるYouTubeビデオ講義付き】

中学英語の基本を学年別・単元別に学ぶ、書き込み式薄型問題集シリーズです。
「中学生のときに英語が本当に苦手だった」と自認する著者がつくるテキストは、英文法を基礎の基礎から丁寧に解説し、豊富な問題で繰り返し英文を書かせるのが特徴です。前に習ったことの復習が何度も出てくるので、自分の弱点を知って、正しい英語を身につけることができます。
「たくや式 どんどん読める 中学英語長文」全4巻
【著者によるYouTubeビデオ講義付き】
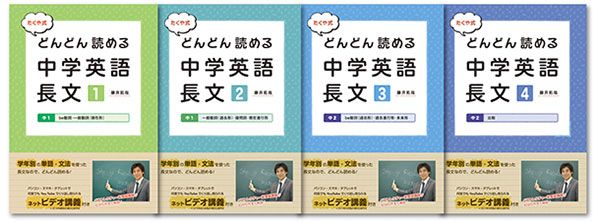
学年別の単語・文法を使ったオリジナル長文(会話文・メールの文章・ブログの文章・講義など)を各巻11話収録。どの学年の方も、無理なくどんどん長文が読める仕組みになっています。定期テストや入学試験でよく出題される穴埋め問題や、文脈把握問題のほか、たくや式ならではの、「英語の文法を自分の言葉で説明できるか」を問うたくさんの問題を収録。
※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。




