
解体に挑戦
海のプラスチックごみが問題になっています。さかなクンといっしょに海の研究をすすめる「さかなクン探究隊」(主催・青い地球を育む会)は9日、東京都港区の東京海洋大学品川キャンパスで、この問題にくわしい先生に話を聞きました。魚がプラをのみこむこともあるようです。試しに深海魚ミズウオを解体してみると……!(小貫友里)
弁当のしきり、漁具の切れはし、袋…
前回の活動で、隊員たちは神奈川県鎌倉市の海岸でごみ拾いをしました。きれいに見える砂浜にもたくさんプラごみがありました。5ミリ以下になった「マイクロプラ」もふくめると、拾いきるのは「無理!」と感じたそうです。
今回は、海のごみ問題にくわしい東京海洋大学教授の内田圭一さんに解説してもらいました。
隊員たちは魚などを食べるミズウオの解体に挑戦。おなかを切ると、胃から小魚が出てきました。しばらくすると「あった!」。プラでできたお弁当のしきり、漁具の切れはし、外国語が書いてある袋の一部などが見つかりました。
ミズウオはなんでも口に入れるため、海のよごれ具合の調査にも使われます。「ミズウオからごみが出る確率がだんだん上がっているという研究もあります」と内田さん。

生活に欠かせないプラ
一方、プラは食べ物や薬をきれいなまま保存できるなど、大事な役割も果たしています。内田さんは「プラは優秀で、私たちの生活に不可欠です。問題を解決しながらプラと付き合わなければなりません」と呼びかけました。
活動を通して、大西啓翔さん(5年)は「ごみが川に流れないよう見つけたら拾ったり、川でごみを取る活動などに参加したりすることが大切」と話していました。
品川キャンパスの施設を見学


おしえて内田先生!
なぜ海のプラスチックが問題なの?
「汚染物質とくっつきやすく、生物の体にたまってしまう」
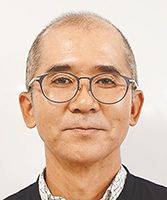
人間もほかの生き物も、きれいなプラは取りこんでも体の外に出せるので、基本的に問題はないといわれます。ではなぜ海のプラが問題なのでしょう。それは、海のマイクロプラが化学物質をためこんでいるからです。
プラが海に出ると日光や波の影響でくだかれ、細かくなり、マイクロプラになります。プラは海の汚染物質とくっつきやすい性質があります。汚染物質をふくむマイクロプラを生き物が食べると、「食べる・食べられる」関係の上位にいるサメやクジラなどに汚染物質がたまります。これを「生物濃縮」といいます。
いま、世界のどの海でもマイクロプラが見つかっています。特に日本のまわりの海では、世界の海の平均的な量の約27倍。東アジアや東南アジアは世界でみても、海に流れるプラごみが多いようです。
漁師さんの網にたくさんプラごみが入ってとれる魚が減ったり、水の重みもかかって網がやぶけたりすることもあります。漁師さんにもプラごみ問題は一大事です。
海に出たプラを取りきるのはむずかしい。そのため、出す量を減らすことが大切なのです。

(朝日小学生新聞2024年11月16日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。




