
累計発行部数7万部突破「たくや式」英語問題集シリーズの著者・藤井拓哉さんが、家族でのアメリカ生活や家庭での英語学習についてつづります。
季節ごとに習うスポーツを変える
アメリカでもスポーツの習い事は人気! しかし、アメリカの場合、スポーツがシーズンによって分けられており、高校までは、複数のスポーツを経験させることが多い。例えば、春はテニスやバレーボール、夏から秋にかけてはサッカーやアメリカンフットボール、冬は水泳やバスケットボールというようになっており、日本では一般的な「1つのスポーツを年間通して行う」という考えはあまり一般的ではない。この背景には、「さまざまなスポーツを通じて子どもの潜在能力を見つける」「体のいろいろな部分を使ってバランス良く体を鍛えていく」という考えがあるからだ。個人的には「サッカー or 野球」ではなく「サッカー and 野球」という子どもの可能性を残すアメリカの考え方は、子どもの燃え尽き症候群を防ぐという意味でも理にかなっている気がする。
親によるボランティアコーチにはメリットも
アメリカの地域スポーツを支えているのが、ボランティアコーチの存在だ。日本でもそうだが、スポーツクラブの多くは子どもの親がチームのコーチやアシスタントコーチを務めている。しかし、アメリカのスポーツクラブでは、コーチ特典がある場合が多い。例えば、チーム参加費の一部または全額が免除されたり、コーチの研修プログラムやトレーニングも提供され、指導技術を学ぶことができたりするのだ。実は、私も息子たちのサッカークラブのコーチをし、息子たちのクラブ参加費用を無料にしてもらった。
アメリカのサッカークラブで興味深いと思ったのが「小学校低〜中学年の子どもたちがプレーするリーグでは試合や練習中にヘディングを行わないよう指導される」という点。この背景には、幼いころに頭部に衝撃を受けることで、後の人生で脳に障害が出る可能性があるという医学的見解があるとか。
同様の理由で、アメリカンフットボールにも工夫が施されている。通常のフットボールではタックルを伴うプレーが多く含まれるが、子どもたちにはより安全な代替競技である「フラッグフットボール」が推奨されている。この競技では、タックルの代わりに腰につけたタスキ(フラッグ)を引き抜くことで「タックルされた」とみなされる。この形式は身体的接触を大幅に減らすため、怪我のリスクを最小限に抑えながら、フットボール特有の戦略やスキルを学べるようになっている。

アメリカの「部活」はもはやミニプロスポーツ⁉
「アメリカには日本のような部活はないの?」というと……あるけど全然違う! アメリカでも中学校や高校から部活のようなスポーツチームが始まるのだが、その運営スタイルはかなり違う。すでに紹介した通り「シーズン制」であることもそうなのだが、一番驚かされるのが「試合観戦が有料の場合がある」という点だ。水泳やテニスなどあまりメジャーでないスポーツの場合、観戦チケットは不要なのだが、アメリカンフットボールやバスケットボールのような人気スポーツでは、通常観戦チケット必要となる。私の住む地域では、チケット代は大人1人$10、日本円にすると約¥1,500と、もはやプロのマイナーリーグ並みの値段だ(ちなみに高校生や中学生のチケットは若干安め)。
しかし、人気のスポーツともなると迫力はかなりのものとなる。観客席には保護者だけでなく、ボディーペイントをした生徒や、チアリーダー、マーチングバンドがパフォーマンスを繰り広げ試合を盛り上げる。また売店も設置されているため、ホットドッグ、ピザ、ポテトチップス、コーヒー、ジュースといった食事や飲み物も買うことができ、雰囲気はまるでプロの試合のようだ。
学校のスポーツで得た収益の使い道は?
「プロの試合のような盛り上がりなのであれば、収益も相当なものなんじゃないの? いったいそれらのお金は何に使われるの?」と気になるところだろう。実はかなり合理的に使われている。
1. チームや施設の維持
a) 新しい用具やユニフォーム代。
b) 施設の維持費:スタジアムの照明やグラウンドの芝生管理代など
c) 移動費: 試合の際の移動は基本スクールバス
d) コーチの給与: 専属コーチやアシスタントの報酬など
2. 他のスポーツへの支援
a) 収益を生み出しにくいスポーツ(例:水泳、テニスなど)のサポート
3. 試合運営費用
a) 試合時の審判やセキュリティスタッフの費用
このように見ると、チケット代や売店収益は「お金集め」ではなく、学校全体の部活を支えるための重要な資金源になっていることが分かる。
アメリカの子どものスポーツ事情を覗いてみると、日本とは異なる点がいくつか見えてくる。「シーズン制」を採用し、複数のスポーツに取り組むことで、子どもの可能性を広げ、バランスの良い成長を促す。また試合運営がまるでプロのように行われているのも興味深い。
現在、部活の見直しがされている日本。「1年中、同じスポーツに打ち込む」というスタイルは中途半端にならないという意味で適しているが、アメリカのように「様々なスポーツに取り組める」といったスタイルも選べるようになると更にスポーツが楽しめるのではないだろうか。

藤井拓哉(ふじい・たくや)

1984年生まれ。父親の都合で3歳~6歳までと、15歳~24歳までをアメリカのオハイオ州で過ごす。オハイオ州立大学、同大学院で教育学を学び、日本語の教員免許とTESOL(英語を母国語としない方のための英語教授法)を取得。帰国後は、宇都宮大学で英語講師を務める。数学、化学、生物学、物理学を英語で学ぶ「理数系英語」の講義を定期的に行い、2010年と2013年に学生による「授業評価アンケート」をもとに選ぶ「ベストレクチャー賞」を受賞。その後、上智大学、筑波大学などで英語講師を務めた後、2023年から家族でアメリカ暮らしを始める。著書に『たくや式中学英語ノート』シリーズ(朝日学生新聞社)、『MP3CD付き ガチトレ 英語スピーキング徹底トレーニング』シリーズ(ベレ出版)。TOEIC955点、TOEFL101点。
「たくや式中学英語ノート」全10巻
【著者によるYouTubeビデオ講義付き】

中学英語の基本を学年別・単元別に学ぶ、書き込み式薄型問題集シリーズです。
「中学生のときに英語が本当に苦手だった」と自認する著者がつくるテキストは、英文法を基礎の基礎から丁寧に解説し、豊富な問題で繰り返し英文を書かせるのが特徴です。前に習ったことの復習が何度も出てくるので、自分の弱点を知って、正しい英語を身につけることができます。
「たくや式 どんどん読める 中学英語長文」全4巻
【著者によるYouTubeビデオ講義付き】
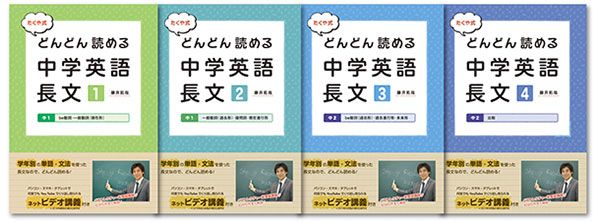
学年別の単語・文法を使ったオリジナル長文(会話文・メールの文章・ブログの文章・講義など)を各巻11話収録。どの学年の方も、無理なくどんどん長文が読める仕組みになっています。定期テストや入学試験でよく出題される穴埋め問題や、文脈把握問題のほか、たくや式ならではの、「英語の文法を自分の言葉で説明できるか」を問うたくさんの問題を収録。
※本サイトに掲載されるサービスを通じて書籍等を購入された場合、売上の一部が朝日学生新聞社に還元される事があります。




