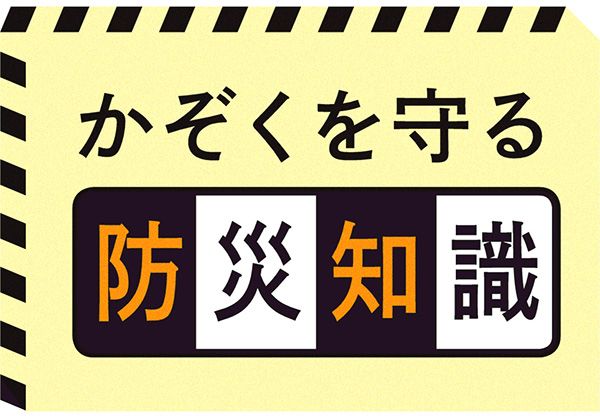
災害時、家族との連絡方法
● スマホがつながらない
災害が発生すると安否確認電話が殺到。かからないと何度もかけ直すため回線や交換機の許容量をはるかに超えてしまいます。そうなると電話接続が滞るだけでなく、やがてはシステム全体が停止する恐れがあります。
そこで交換機を守ると共に、警察、消防などの重要通信を確保するため、異常を検知すると許容量を超えないように一般電話の接続が制御・規制されます。
また、基地局の非常電源は数時間から1日程度のバックアップ容量しかありませんので、停電が長引くとスマホが長時間つながりにくくなり、離ればなれの家族と連絡が取りにくくなります。昨年の能登半島地震直後、電話もメールも長時間つながりにくくなり、家族と連絡が取れない被災者は不安と焦燥にさいなまれました。
● 三角連絡法
そんな時、頼りになるのが公衆電話です。停電でも使用でき、通信規制も受けないので災害時でもつながりやすいのです。ただ、20年前には全国に73万台あった公衆電話も今は約8万台に減っていますので、近くの設置場所を確認しておく必要があります。
そして、公衆電話から通信規制エリアにかけてもつながりにくいので、災害伝言ダイヤル「171」にかけるか、あらかじめ決めておいた被災エリア外の親戚などを中継所にして、家族が連絡を取り合う「三角連絡法」がお勧めです。被災地から被災地外へは規制が限られるのでつながる可能性が高いからです。
こうした緊急連絡メモは家族全員が常に携行するようにしましょう。また、子どもさんには今のうちに公衆電話の使用法を教えておき、毎月1日、15日などの体験利用日に家族全員で171連絡訓練を行うといいですね。

● SNSの家族グループ
私の体験では、いくつかの災害現場で比較的つながりやすかったのがSMS(ショート・メッセージ・サービス)でした。メールアドレスが分からなくても携帯電話番号にメッセージが送れます。そして受信時にはポップアップが表示されるので、着信に気付きやすいのも利点です。
またLINEは、震度6以上の地震などの災害発生時、ホームタブに表示される「LINE安否確認」の「安否を報告」をタップすれば、家族や友達と情報を共有できます。LINEだけでなく、FacebookやXなどの「グループ機能」も普段から家族連絡用として使っていれば、いざという時スムースに安否確認ができます。いずれにしても災害時の緊急連絡手段は複数準備しておくと安心です。
山村 武彦(やまむら たけひこ)
防災システム研究所所長。東京都出身。実践的防災・危機管理の第一人者。1964年、新潟 地震でのボランティア活動を契機に、研究所を設立。以来50年以上、世界中で発生する災害の現地調査を実施。報道番組での解説や講演、執筆活動などを通して防災意識の啓発に取り組む。企業や自治体の社外顧問やアドバイザーを歴任。防災・危機管理マニュアルの策定など、災害に強い街づくりに携わる。座右の銘は「真実と教訓は、現場にあり」。
(みんなをつなぐ新聞2025年7月20日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。




