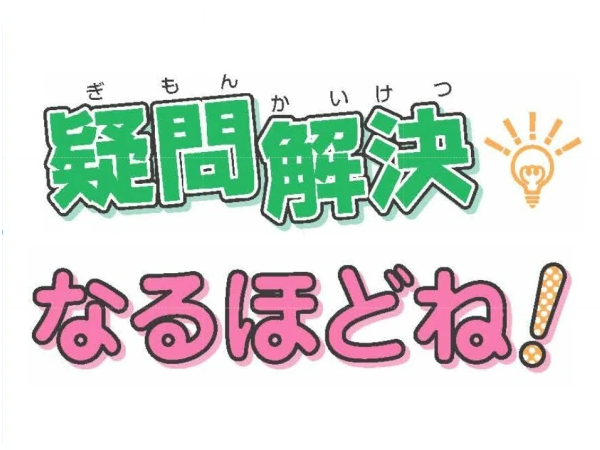
読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回はSさん(栃木県・4年)から寄せられた「しぶ柿干すとなぜあまくなる?」という質問に答えます。
Sさん(栃木県・4年)の疑問
干し柿を作りました。干す前に少しかじったら、すごくしぶかったのに、できあがったらすごくあまかったです。なぜしぶくなくなるのですか。
奈良県農業研究開発センター加工科長・浜崎貞弘さんの回答
皮をむいた柿の中で起きる化学反応が、しぶ味のもとのタンニンという成分を固めてしまいます。タンニンが口で溶けないため、しぶさを感じなくなります。
ストレスあたえ、しぶ味のもと固める
しぶさは植物界で一番

質問に答えてくれたのは、奈良県農業研究開発センター加工科の浜崎貞弘さんです。『柿づくし』という本も書いています。
しぶ味のもとは柿にふくまれるタンニンという成分です。お茶やブドウにも似たような成分はありますが、浜崎さんは「柿のしぶさは植物界で一番ではないでしょうか」といいます。このタンニンがもう一つ群をぬいているのが「いろいろなものとくっつきやすい性質」です。そのため「しぶぬき」ができるのです。
柿は果実の表面ではなく、ヘタの部分で呼吸をしています。呼吸は収穫したあとも続いています。皮をむくとストレスを感じて呼吸が激しくなり、柿の中でアルコールができます。アルコールが化学反応を起こしてできるアセトアルデヒドという物質は、タンニンとくっついてタンニンを固めてしまいます。
固まったタンニンは口の中で溶け出さないので、食べてもしぶ味を感じなくなります。「しぶぬき」とはいいますが、タンニンはなくなったわけではありません。一度にたくさんの柿を食べると、おなかの中でタンニンが悪さをするので注意が必要です。
ヘタにお酒をかけてアルコールを吸わせたり、お湯の中に浮かべて窒息させたりというのも、古くから行われてきたしぶぬきの方法です。
晴れの日が続くときに干そう
日本には約1千品種の柿があるといいます。そのうち60~70%はしぶ柿の品種です。あま柿が少ないのは、雄花が少ないので子孫を作りづらく、また、岐阜より北では育ちにくいためです。

日本の三大品種は富有、平核無、刀根早生です。富有以外はしぶ柿です。でも、お店で買って食べてもしぶくないのは、出荷前に炭酸ガスの部屋に入れてしぶぬきをしているからです。
柿はもともとしぶ柿しかありませんでした。鎌倉時代、今の神奈川県川崎市にある王禅寺であまい実が見つかりました。これが国内で記録に残る最初のあま柿「禅寺丸」です。現在は近くに「柿生」という駅もあり、あま柿発祥の地として秋には祭りも開かれています。
カビが生えないように
干し柿に向く品種は、平核無、甲州百目、市田などだそうです。平核無、甲州百目はやわらかく、市田は小さくて弾力のある干し柿になります。作るときは「カビが生えないように極力早くかわかすこと」。浜崎さんは「週間天気予報を見て晴れの日が続くときを見計らって作業を」とアドバイスします。表面だけでも完全にかわけばカビは防げます。

今はこれだけ柿とかかわりのある浜崎さんですが、小さいころは柿が苦手だったそうです。「酸味のあるあまさのほうが好きだったんです。でも、あま味や色を生かして、大根のなますや白菜のサラダに入れるのもいい。乳製品と合うのでヨーグルトと食べるのもおすすめです」
(朝日小学生新聞2022年11月1日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。







