『鬼滅の刃』に出てくる刀鍛冶の仕事を取材してみたい――。朝小リポーターのらくさん(小5)から、編集部にこんなメールが届きました。まんがやアニメ、ゲームに登場する日本刀は、武士がいなくなった今の時代でもつくられているのでしょうか? いっしょに訪ねた刀鍛冶の仕事場には、たくさんの「びっくり」が待っていました。(編集委員・別府薫)
こども記者が見つけた三つの「びっくり」

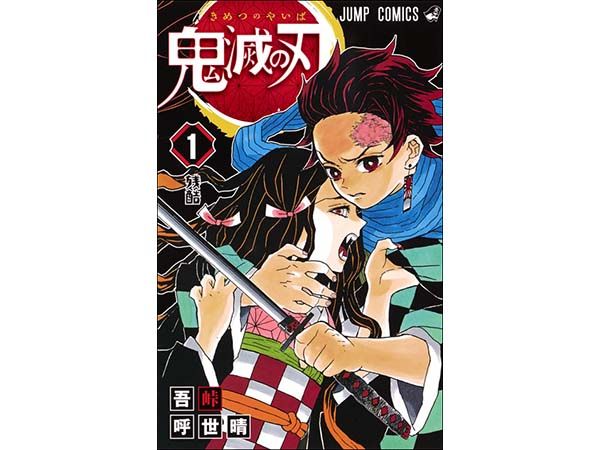
灼熱の「鍛錬」 1万もの鋼の層をつくる
取材に向かったのは、群馬県富岡市にある鍛刀場です。刀鍛冶の石田國壽(くにひさ)さん(48歳)に、刀をつくる工程のひとつ「鍛錬(たんれん)」を見せてもらいました。

うす暗い室内で、石田さんはパチパチと燃え上がる炎を見つめています。真っ赤に燃える炭の中で刀の原料・玉鋼(たまはがね)を熱しているのです。玉鋼とは、砂鉄に炭素を加えてつくった鉄の合金です=2ページ目の「まめ知識」を見てね。「ふいご」という道具で空気を送ると、ごうごうと炎の勢いが増しました。

『鬼滅の刃』に登場する刀鍛冶たちは、ひょっとこのお面をつけています。ひょっとこは、かまどの火を守る「火男(ひおとこ)」がもとになっているという説がありますが、どうしてお面をつけるのでしょうか。らくさんが質問をすると、「まんがの世界だからわからない」と石田さんは笑います。実際には、炎の色を確かめるために素顔で作業します。手袋も、かえってひどいやけどにつながるので、しないそうです。
赤みがかった炎の色は、温度があがるにつれてオレンジ色から黄色へ。鉄がとけ始める約1500度に近づいてきたサインです。とける一歩手前で玉鋼を取り出し、機械のハンマーでたたきます。

ガンガンガンとすさまじい音で火花を散らしながらたたいてのばし、折り返します。とかすのではなく、たたいてくっつけることで鋼の層ができます。

鍛錬をくり返し、さまざまな工程をへて完成した刀は、およそ1万もの層が重なります。折り返すたびに倍になるので、刀によっては2万層を超えることもあるそうです。
刀の形がととのったら、熱してから水で急激に冷やす「焼き入れ」をして刃をかたくします。こうして、よく切れて、折れにくい刀ができるのです。
炎の色を見て作業することにびっくりしました。木炭を使うのは火力よりも炎のまわり方を気にしているからということに、なるほど~と思いました。

まめ知識 あいづちを打つ

相手の話に調子を合わせる「あいづちを打つ」という言葉は、刀の鍛錬から生まれました。玉鋼をのばすとき、古くから伝わるやり方では、ふたりひと組で「槌(つち)」という道具でたたきます。玉鋼をおさえる人は、槌を打つ人にふりおろすタイミングなどを知らせるために小さな槌をたたいて合図します。これを「あいづちを打つ」といいます。
玉鋼をたたく槌を持たせてもらったらくさんは、その重さにびっくり。7キロもあるそうです。ねらったところに正確にふりおろす技術を身につけなくては一人前になれないと聞き、さらにおどろきました。





