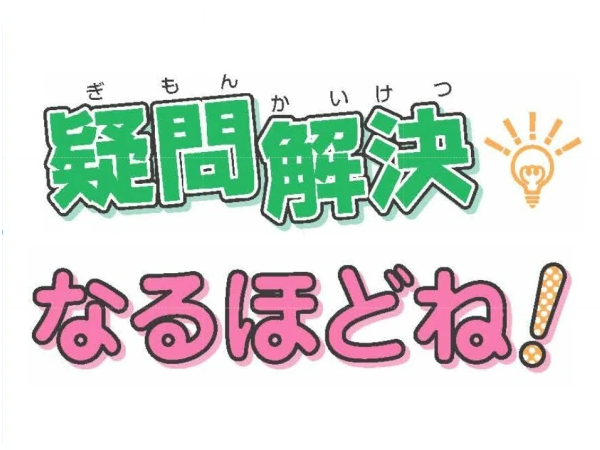
読者から寄せられた疑問を編集部が調査するコーナーです。今回は群馬県の小学4年生、Iさんから寄せられた「パソコンのキーボードは何の順?」という質問に答えます。
Iさん(群馬県・4年)の疑問
私は学校で勉強にタブレットを使っています。タブレットのキーボードは、あいうえお順でもABC順でもありません。何の順番なのでしょうか?
NECパーソナルコンピュータ商品企画本部マネージャー 中井裕介さんの回答
パソコンが発明されるずっと前に使われていた、タイプライターのキーの並び方がもとになっています。なんと140年前からほとんど変わっていないのです。
英語での使いやすさを求めた結果?
140年前に今の形に
質問に答えてくれたのは、NECパーソナルコンピュータ商品企画本部の中井裕介さんです。パソコンを15年担当していますが、キーボードの長い歴史については知らないことも多く、今回調べてみたそうです。
「キーの並び方はタイプライターからきています。1880年代にはすでに今の配列になっていました」と言います。タイプライターは、指でキーをおして文字をはんこのように印字する機械です。
なぜこの並びになったかにはさまざまな説があるそうです。中井さんがずっと信じていたのは「わざと打ちづらい配置にした」という説です。タイプライターの印字は電気ではなく機械式なので、あまり速く打つとこわれやすくなるからということです。
「営業マンが売りやすいようにした」という説もあるそうです。タイプライターの英語のつづりは「TYPEWRITER」。これらの文字は、アルファベットキーの一番上の列にすべてふくまれています。お客さんの前で実演しやすいようにしたという説です。
ただ、今回調べて中井さんが最も納得したのは「発明されて間もない1870年代はアルファベットの並び順に近かったが、英語の打ちやすさなどに合わせていくうちに今の形になった」という説です。
それから約半世紀後の1930年代に、よく使うキーを真ん中に固める配置が考えられましたが、広まりませんでした。中井さんは「すでに定着したものに慣れてしまっていたからでしょう」と言います。
日本語独自の形や配置も
日本のキーボードには、ひらがなもついています。ひらがな入力のためですが、今は9割以上がローマ字入力だといいます。
英語は変換キーなし
他にも、日本語用と英語用のキーボードにはちがいがあります。決定や改行に使う「Enter」キーと、「変換」「無変換」のキーです。日本語用はEnterキーが大きく、逆L字形で目立ちます。英語用には変換、無変換のキーはなく、一番下の中央にある、1字空きのキーがその分大きくなっています。

日本語はひらがなを漢字に変換したあと、決定しなければなりません。英語は変換の必要がありませんが、単語ごとに1字空けます。日本語の文章は改行が多いのに対し、英語は改行せずに続けて書くことが多いそうです。
「基本は同じでも、言語や文章の書き方で少しちがってくる。パソコン業界ではEnterキーは『日本の心』と言っているんですよ」と中井さん。キーボードの右側にあるかぎかっこや@などの記号は、1980年代に国内で配置を統一しました。
配列は変えられなくても工夫をこらしています。NECではここ10年ほどで、ノートパソコンのキーとキーの間のすき間を広げました。さわってすぐにちがうキーであることがわかり、長い爪を引っかけてキーが取れたりしないようにです。(中田美和子)
キーを見ないで打てるようになるには?
「F」と「J」のキーには小さな出っ張りがあります。ここに人指し指をのせるのがホームポジション。この形を変えずに指を上下にななめに動かして打つのが基本です。あとはどのキーをどの指で打つかを覚え、ひたすら練習するのみです。(中井さん)
(朝日小学生新聞2023年2月21日付)

「朝小プラス」は朝日小学生新聞のデジタル版です。毎日の読む習慣が学力アップにつながります。1日1つの記事でも、1年間で相当な情報量に!ニュース解説は大人にもおすすめ。







